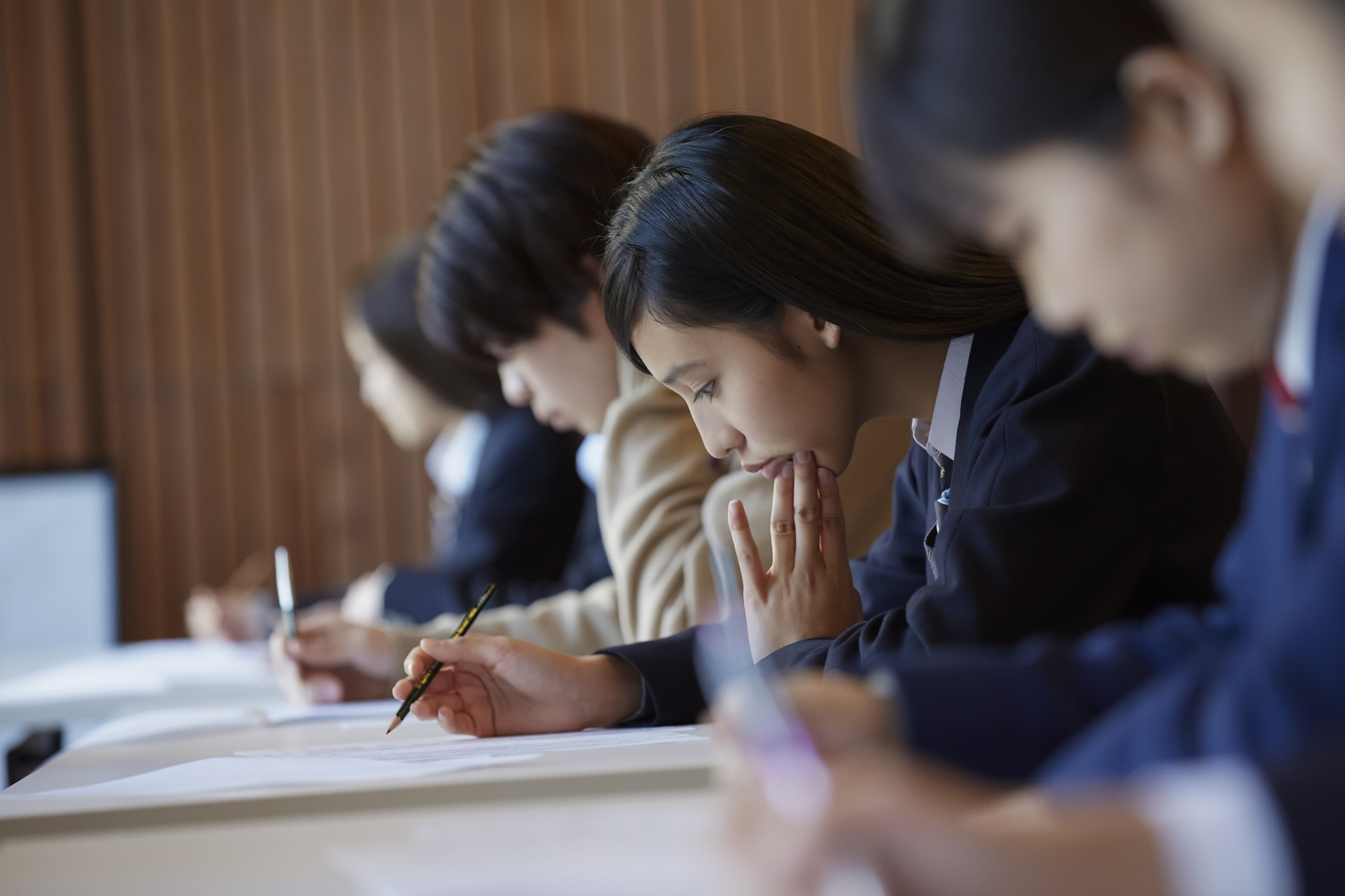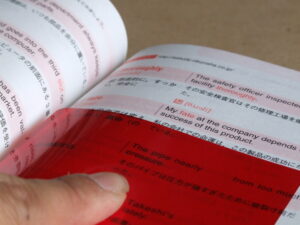「大学受験の合否は、個別学力検査(二次試験)の出来で決まる」
そう思っていませんか?
もちろん二次試験は重要ですが、実はその前に、合否を分ける非常に重要な関門があることをご存じでしょうか。それが、今回詳しく解説する「第一段階選抜」です。
もしあなたが第一段階選抜について何も知らずに受験に臨んでしまうと、志望校の二次試験すら受験できず、合格のチャンスを失ってしまうかもしれません。
しかし、安心してください。この記事を最後まで読めば、第一段階選抜に関するあらゆる疑問や不安が解消され、どうすればこの関門を突破できるのか、具体的な対策まで手に入れることができるでしょう。
第一段階選抜とは共通テストの点数で二次試験の受験資格を失う制度
多くの国公立大学で採用されている第一段階選抜とは、大学入学共通テスト(以下、共通テスト)の成績が、大学の定めた基準に達しない場合、個別学力検査(二次試験)を受験することができなくなる制度を指します。
つまり、共通テストの点数が芳しくないと、どんなに二次試験が得意でも、その力を発揮する場すら与えられない可能性がある、受験生にとって非常に重要な「ふるい」のようなものなのです。
この制度は、国公立大学の一般選抜で実施されており、特に難関大学や人気の学部で適用される傾向があります。
なぜ第一段階選抜は行われる?大学側の2つの主な理由

受験生にとっては厳しい制度である第一段階選抜ですが、なぜこのような選抜が行われるのでしょうか? 大学側の視点から見ると、主に以下の2つの合理的な理由があります。
理由1:二次試験の採点の質と公平性を担保するため
国公立大学の二次試験では、論述式や記述式の問題が多く出題されます。これらの採点には、非常に専門的な知識と膨大な時間、そして労力が必要です。全ての志願者の答案を丁寧に採点しようとすると、限られた期間内での合否判定が困難になる可能性があります。
第一段階選抜を実施することで、二次試験を受験する人数を絞り込むことができ、それによって採点官の負担を軽減し、より質の高い、公平な採点を行うことが可能になります。 これにより、合否判定の信頼性を保ちながら、スムーズな入試運営を実現していると言えるでしょう。
理由2:試験会場の収容人数(キャパシティ)に限りがあるため
大学の試験会場には、物理的な収容人数の限りがあります。志願者が予想をはるかに超えて殺到した場合、全ての受験生を収容できるだけの十分な試験室や監督者を確保することが難しくなります。
第一段階選抜は、試験会場のキャパシティを超える志願者があった場合に、物理的な制約の中で円滑な試験運営を行うための手段でもあります。これにより、受験生全員に適切な受験環境を提供しつつ、安全かつ効率的な入試実施を可能にしています。
【仕組み】第一段階選抜の具体的なルールと2つのパターン

第一段階選抜の基本的な定義を理解したところで、次に「どのようにして第一段階選抜が行われるのか」という具体的なルールや仕組みを深掘りしていきましょう。仕組みを知ることは、あなたが自身の状況を正しく判断し、適切な受験戦略を立てる上で不可欠です。
第一段階選抜には、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。
パターン1:予告倍率による第一段階選抜
最も一般的な第一段階選抜のパターンは、大学が募集要項にあらかじめ「予告倍率」を記載しているケースです。
例えば、「志願者数が募集人員の〇倍を超えた場合に第一段階選抜を実施する」といった形で明記されています。
具体的には、
- 募集人員が100人の学部に、「予告倍率5倍」と記載されている場合、志願者数が500人(100人 × 5倍)を超えると第一段階選抜が実施される可能性があります。
- この場合、500人を超える志願者の中から、共通テストの成績が上位500人程度(大学によって調整される)の受験生のみが二次試験に進むことができます。
このパターンでは、共通テストの成績だけでなく、その年の志願者の動向(倍率)によって、第一段階選抜の実施の有無や合格ラインが変動するのが特徴です。志願者が少なければ第一段階選抜が実施されないこともあり、逆に志願者が多ければ厳しい選抜が行われることになります。
パターン2:最低点による第一段階選抜
もう一つのパターンは、志願倍率に拘らず、共通テストの合計点や特定の科目の得点が、大学が設定した「最低点」に満たない受験生を不合格とするケースです。
この方式は、特に医学部医学科など、高い学力を求める大学・学部で採用されることが多い。例えば、「共通テストの合計点が〇点未満の者は第一段階選抜で不合格とする」といった具体的な得点基準が設けられている場合があります。
この最低点は、毎年変動することもあれば、固定されていることもあります。このパターンでは、たとえ志願倍率が低くても、大学が求める最低限の学力水準に達していないと判断されれば、二次試験に進むことはできません。
両方のパターンを併用する大学も存在します。
例えば、「志願者数が予告倍率を超えた場合に第一段階選抜を実施し、かつ共通テストの最低点を満たさない場合は、その予告倍率に達していなくても第一段階選抜で不合格とする」といった複雑なルールを設けている大学もあります。
そのため、志望校の「入学者選抜要項」や「募集要項」を熟読し、どのパターンが適用されるのか、具体的な条件はどうなっているのかを正確に把握することが不可欠です。見落としがないよう、隅々まで確認するようにしましょう。
第一段階選抜の合格ラインと判明するタイミング

受験生が最も気になるのは、やはり第一段階選抜の合格ラインがどのように決まり、いつ判明するのか、という点でしょう。
ここでは、合格ラインの決まり方から、第一段階選抜が実施されやすい大学の特徴、そして最終的に結果が判明するまでの流れを時系列で解説します。
第一段階選抜の合格ラインは毎年変動する
「昨年の合格ラインは〇点だったから、今年もそのくらいで大丈夫だろう」
このように考えてしまうのは危険です。なぜなら、第一段階選抜の合格ラインは固定ではなく、毎年変動するからです。その変動には、主に以下の3つの要素が複雑に絡み合っています。
- その年の共通テストの平均点: 共通テストの難易度によって平均点は大きく変動します。平均点が上がれば合格ラインも上がる傾向にあり、下がれば合格ラインも下がる可能性があります。
- 志願者の動向(倍率): 志願者が増えれば、当然ながら合格ラインは上がります。逆に、志願者が減れば合格ラインが下がることもあります。人気の大学・学部ほど、この影響を大きく受けます。
- 大学・学部ごとの難易度: そもそもの大学・学部の人気や難易度が高いほど、合格ラインも高くなる傾向にあります。
したがって、前年度の合格ラインはあくまで参考値と捉え、それに固執し過ぎないことが重要です。常に最新の情報を入手し、柔軟に対応する姿勢が求められます。
志望校の第一段階選抜のラインの調べ方
では、志望校の第一段階選抜のラインを予測するにはどうすればよいのでしょうか?
まず最も重要なのは、大学公式の「入学者選抜要項」や「学生募集要項」を細かく確認することです。ここに、第一段階選抜実施の有無、予告倍率、あるいは最低点といった具体的なルールが記載されています。
その上で、共通テスト受験後に行われる予備校の「自己採点集計データネット」の結果や、過去の入試データを参考に、今年度の通過ラインを予測します。 複数の予備校が提供するデータを比較検討することで、より精度の高い予測が可能になります。
これらのデータは、全国の受験生の共通テストの得点状況や、志望校に対する出願動向をリアルタイムで把握するための強力なツールとなります。
第一段階選抜が実施されやすい大学・学部の特徴
毎年、あるいは隔年で第一段階選抜が実施される可能性が高い大学・学部には、ある程度の傾向が見られます。具体的には、以下のような特徴を持つ大学・学部は、第一段階選抜が行われやすいと考えられます。
- 旧帝大(東京大学、京都大学など)や難関国公立大学: これらの大学は全国から優秀な受験生が集まるため、志願者が多く、競争が激しくなりやすい。
- 医学部医学科: 医師を目指す受験生が非常に多く、全国的に高い人気を誇るため、第一段階選抜が行われることが珍しくありません。
- 都市部の一部の人気大学・学部: 大都市圏にある人気大学の特定の学部は、アクセスや研究内容、就職実績などから志願者が殺到しやすく、第一段階選抜が実施される可能性があります。
これらの大学・学部を志望する場合は、第一段階選抜の存在を念頭に置き、より一層の共通テスト対策が求められます。
【時系列】第一段階選抜実施が判明するまでの流れ
第一段階選抜が実施されるかどうかが最終的に判明するまでには、いくつかの段階があります。
- 夏:「入学者選抜要項」での告知 多くの大学では、その年の入試に関する詳細を記載した「入学者選抜要項」を夏頃に発表します。この要項の中に、第一段階選抜の有無や、その条件(予告倍率など)が明記されています。
- 11月~12月頃:「学生募集要項」での最終確認 より具体的な出願に関する情報が記載された「学生募集要項」は、秋頃に発表されます。ここにも第一段階選抜に関する情報が記載されていますので、必ず確認しましょう。
- 共通テスト後~出願期間:予備校の自己採点集計 共通テスト終了後、「自己採点集計データネット」などに参加することで、自分の得点がどの位置にいるのか、志望校の第一段階選抜の合格ラインがどうなりそうかを予測できます。この情報が出願判断の重要な材料となります。
- 出願締切後~二次試験前:大学からの公式発表 最も重要なのは、出願締切後に大学から発表される公式情報です。多くの大学は、出願締切後、速やかに第一段階選抜の実施の有無、そしてもし実施される場合は、合格者(二次試験受験資格者)の受験番号などを大学のウェブサイトで発表します。これが、第一段階選抜の結果が最終的に判明するタイミングとなります。この発表を必ず確認し、自身の受験番号があるか確認しましょう。
第一段階選抜に引っかからないための具体的な5つの対策
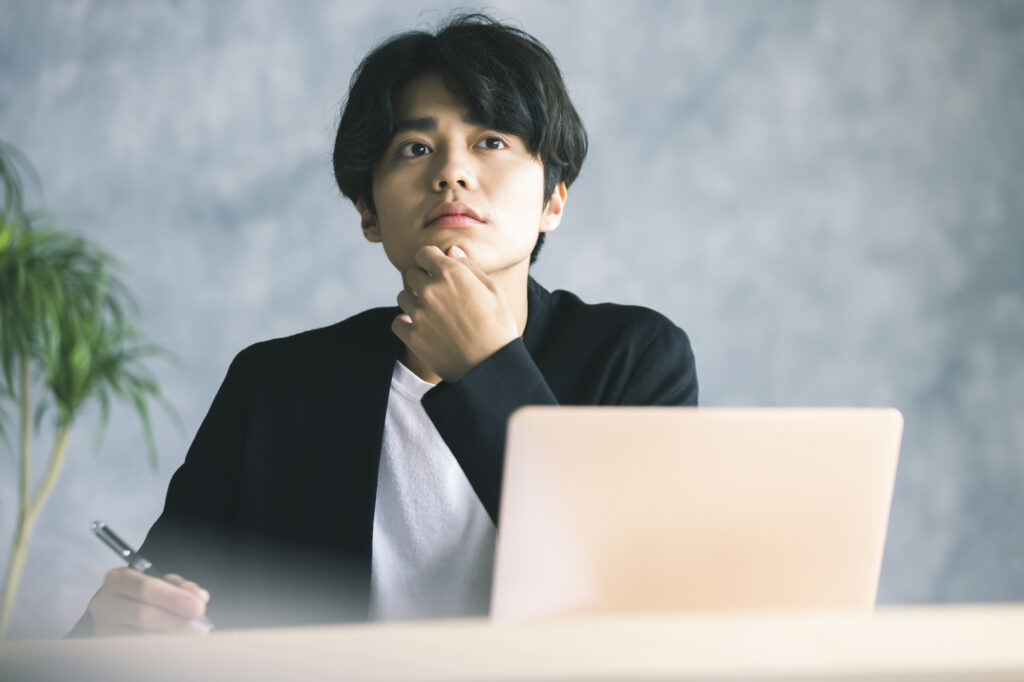
第一段階選抜の仕組みと現状を理解した上で、この関門を確実に突破し、志望校合格への道を切り開くためには、どのような行動をとればよいのでしょうか。
ここでは、データに基づいた戦略的なアプローチを解説し、あなたがすぐに行動に移せる具体的な5つの対策を提示します。
対策①:共通テストで確実に得点する!目標点の設定と学習計画
何よりもまず、全ての基本は共通テストで高得点を取ることです。
「二次試験の配点が高いから、共通テストはそこそこでいいや」と考えてしまうのは非常に危険です。なぜなら、どれだけ二次試験が得意でも、第一段階選抜を突破できなければ、その力を発揮する場すら与えられないからです。
まずは、志望校の過去の第一段階選抜の合格ラインや、合格者平均点(もし公表されていれば)を参考に、第一段階選抜を余裕でクリアできる「目標点」を設定しましょう。その目標点を達成するためには、各科目で何点ずつ取る必要があるのかを具体的に割り出し、そこから逆算して、日々の学習計画を立てていくことが重要です。
例えば、「共通テストで〇〇点以上取る」という具体的な目標を掲げ、苦手科目の克服や得意科目のさらなる伸長に努めましょう。計画は具体的な数値目標とともに、定期的な見直しも忘れずに行いましょう。
対策②:正確な自己採点の徹底
共通テストを受験した後は、すぐに「終わった!」と開放感に浸るのではなく、非常に重要な作業が待っています。それが、正確な自己採点の徹底です。
- 正確な自己採点: 共通テスト受験後、記憶が新しいうちに解答を問題用紙などに記録しておきましょう。そして、試験日の夜や翌日に予備校などが発表する解答速報を用いて、正確に自己採点を行うことが何よりも重要です。たった数点の誤差が、第一段階選抜の合否に影響を及ぼす可能性もゼロではありません。マークミスがないかなども含め、複数回確認するくらいの慎重さが必要です。
- 自己採点集計への参加: 自己採点後は、予備校が実施する「自己採点集計データネット」などに必ず参加しましょう。これは、全国の受験生が自己採点結果を入力することで、自分の得点が全国の受験生の中でどの位置にいるのか(順位や判定)、志望校における自分の立ち位置を客観的に把握できる非常に貴重なデータです。このデータを見れば、第一段階選抜の合格ラインがどのくらいになりそうか、ある程度の予測を立てることができます。
対策③:出願戦略を立てる(予備校データの活用法)
正確な自己採点と自己採点集計データネットの結果を基に、いよいよ最終的な出願校を決定するプロセスです。ここでは、以下の点を考慮して、戦略的に出願先を検討しましょう。
- 予備校の「第一段階選抜予想ライン」や「合格ライン」の比較検討: 各予備校が発表する第一段階選抜予想ラインや合格ラインは、それぞれ算出方法やデータ母体が異なるため、多少のずれが生じることがあります。複数の予備校のデータを比較検討することで、より多角的な視点から自分の立ち位置を把握し、精度の高い予測を立てることができます。
- 自分の得点と合格ラインの比較: 自分の共通テストの得点と、予備校の予想する第一段階選抜の合格ラインを比較しましょう。合格ラインを大きく上回っていれば安心感がありますが、もしギリギリのラインであれば、慎重な判断が必要です。
- 志願者動向(昨年度からの増減)の考慮: 各大学の志願者速報が発表され始めたら、昨年度からの志願者数の増減にも注目しましょう。志願者が大幅に増えている場合は、合格ラインが上がる可能性が高まります。
- 挑戦校と安全校の組み合わせ: 自分の共通テストの得点と、上記の情報を総合的に判断し、挑戦校、実力相応校、安全校を組み合わせた現実的な出願戦略を立てることが大切です。第一段階選抜の突破を最優先に考えるのであれば、共通テストの得点に余裕のある大学・学部を「安全校」として検討するのも一つの手です。
対策④:セカンドプランの準備
万が一、第一段階選抜で不合格となってしまった場合のことを考えて、セカンドプランをあらかじめ検討しておくことも非常に重要です。
国公立大学の中期日程や後期日程への出願準備、あるいは私立大学の一般選抜や共通テスト利用入試(後期)など、複数の選択肢を事前に調べておきましょう。
セカンドプランを用意しておくことで、精神的な余裕が生まれ、前期日程に集中できるというメリットもあります。もし前期で第一段階選抜を突破できなかったとしても、「まだ道はある」と前向きに次のステップに進むことができるでしょう。
対策⑤:募集要項の徹底的な読み込み
繰り返しになりますが、志望する大学の「入学者選抜要項」と「学生募集要項」は、隅から隅まで徹底的に読み込みましょう。
第一段階選抜の実施有無、予告倍率、最低点、そして過去の実施状況など、必要な情報が全てそこに詰まっています。見落としや誤解がないよう、不明な点があれば大学の入試担当部署に問い合わせることもためらわないでください。正確な情報を把握することが、適切な対策の第一歩です。
大学受験の第一段階選抜に関するQ&A

ここまで第一段階選抜の仕組みと対策について解説してきましたが、まだ細かい疑問や不安が残っているかもしれません。ここでは、受験生が抱きがちな質問について、Q&A形式で簡潔に回答します。
Q1. 第一段階選抜に引っかかりそうです…出願変更はすべきですか?
これは非常に悩ましい問題であり、一概に「すべき」「すべきでない」とは言えません。判断の際には、以下の要素を総合的に考慮することが重要です。
- 合格ラインとの差: 自己採点の結果と、予備校が発表する第一段階選抜の予想合格ラインとの差がどれくらいあるか。僅差であれば挑戦する価値はあるかもしれませんが、大きく下回っている場合は厳しい状況と言わざるを得ません。
- 志望度の高さ: その大学・学部への志望度がどれくらい高いのか。第一志望への強い気持ちがあるのであれば、ぎりぎりまで諦めたくないという気持ちも理解できます。
- セカンドプランの状況: 他に受験可能な大学・学部のセカンドプランがどの程度準備できているか。
最終的には、これらの要素を総合的に考慮し、ご自身で決断する必要があります。一人で抱え込まず、学校の先生や予備校の先生、職員、ご家族など、信頼できる人に相談することも強く推奨します。客観的な意見を聞くことで、冷静な判断ができるかもしれません。
Q2. 要項を見たところ、第一段階選抜の予告が書いてありました。どれくらい心配すればいいですか?
第一段階選抜の予告が記載されているということは、「実施される可能性がある」ということです。必ずしも実施されるとは限りませんが、その可能性を念頭に置いて対策を進める必要があります。
心配しすぎる必要はありませんが、以下の点を確認し、準備を進めましょう。
- 予告倍率の確認: 何倍を超えたら実施されるのか、具体的な倍率を確認しましょう。
- 過去の実施状況: その大学・学部で、過去に第一段階選抜が実際に実施されたことがあるのかどうかを調べてみましょう。頻繁に実施されている場合は、今年も実施される可能性が高いと考えられます。
- 共通テスト対策の強化: 第一段階選抜を突破するためには、共通テストでの高得点が不可欠です。改めて共通テストの学習計画を見直し、目標点に到達できるよう全力を尽くしましょう。
予告があるからといって過度に恐れるのではなく、「対策をしっかり行えば突破できる」という前向きな姿勢で臨むことが大切です。
Q3. 浪人したら第一段階選抜で不利になりますか?
入試において、現役生か浪人生かで有利・不利になることはありません。合否は純粋に学力試験の点数のみで決まるため、浪人であることを心配する必要はないでしょう。
まとめ
大学受験の「第一段階選抜」は、共通テストの成績によって二次試験の受験資格が得られなくなる、受験生にとって非常に重要な関門です。しかし、この制度は決して恐れるべきものではなく、正しく理解し、計画的に対策すれば十分に乗り越えられるものです。
第一段階選抜を乗り越えることは、志望校合格への大きな一歩となります。共通テストでしっかりと実力を発揮し、冷静に情報を分析し、戦略的に出願することで、きっとあなたの第一志望合格が現実となるでしょう。