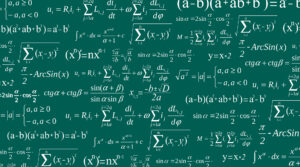進路はあなたの学びたいこと、将来の夢を軸に選びたいものです。しかし、やりたいことが見つからない、まだ漠然としているという人も多いでしょう。
この記事では、学問選びや目標探しのヒントとなるトピックスを紹介します。
投資を学ぶとなにがいいの?【経済学】
経済学の目的・魅力
経済学とは、お金やモノの流れや、人や組織(企業や政府など)の意思決定などを論理的に明らかにすることをめざす学問です。お金が絶対に儲かる法則が見つかれば夢のような話ですが、理想をさらに高く掲げて、「社会や人々を幸福にするための学問」と考えてみましょう。実はとても人間味あふれる学問なのです。
「投資」を知ろう
さて、投資とは将来の利益を見込んで、株式や投資信託などを購入し、長期的に資産を増やしていくことです。その仕組みの1つであるNISAは、2024年から新制度が導入されることもあって、いま注目を集めています。NISAは「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる制度です(金融庁ホームページ)。ちなみにNISAはNippon Individual Savings Accountの略で、イギリスのISA(個人貯蓄口座)をモデルにしています。
日本人と投資の問題
資産を形成する方法は貯蓄と投資がありますが、日本人はこれまで貯蓄を好むとされてきました。
たとえば、この理由を考えることも大学の研究テーマになるでしょう。お金や労働に関する価値観、バブル崩壊後の安定志向、年功序列や終身雇用などの日本的経営といったような社会・福祉・文化・政策などの幅広い問題と関連しています。さらに、そもそも投資は株価変動、信用、金利変動、為替変動などのリスクをともなうものですから、国内外の経済や社会の動向、企業活動について理解が進み、情報を分析する能力も養われます。数学や統計、ITなどを活用するデータサイエンスが有効なアプローチになることも言うまでもありません。
投資で経済を活性化する
少子高齢化により社会保障制度の維持が懸念される中で、老後に備えた個人の資産形成が必要になることはもちろんですし、低金利下で貯蓄だけでは資産を増やすことは難しくなっています。そして、投資は個人だけでなく、企業や国の経済を活性化する効果も期待されます。投資によって企業にお金が集まれば事業を拡大することができるでしょう。2022年4月に東京証券取引所の市場区分が見直され、プライム・スタンダード・グロースに再編されましたが、これは国内外の投資家に対して上場企業の価値をわかりやすく伝え、投資をいっそう呼び込むことが狙いです。
投資はつまりお金が動くことですから、経済が活発になり社会や人々の幸福につながっていくことになるでしょう。
投資に関連する学問分野
具体的には、経済学の中で投資に関係が深いのは、金融論、金融システム、金融政策、ファイナンスなどの分野です。国内外のニュースや社会問題、政治や国際関係などについて幅広く関心をもつとともに、論理的思考力やデータ活用能力が必要で、文系・理系を問わず活躍できるフィールドと言えます。
経営学を学ぶと「就職活動」に強い?【経営学】
経営学の目的・魅力
経営学は、企業が人・モノ・お金・情報などをどのように管理(マネジメント)していけば成果を上げることができるかを研究する学問です。そのためには顧客やステークホルダー(利害関係者)などのニーズを理解する必要がありますから、マーケティングの知見も必要です。
このように、経営学・商学・経済学は密接した関係にあると言えます。企業とコラボレーションしたり、学生たちが自ら起業したり、実践的な学びが展開されています。
就職や進路選択に役立つ経営学
受験生の皆さんにとっては少し先になりますが、大学の学びの大きな目標の一つが就職です。いや、いまの皆さんに決して無関係ではなく、受験も就職も、なにかを選択したり、戦略を立てたりするうえで、経営学の考え方がとても役立つのです。
企業・進路を選ぶヒント
就職活動で犯しやすい過ちの一つに企業研究不足があります。知名度や福利厚生などだけで判断して、よく調べないで応募してしまうケースです。その企業がどのような商品やサービスを提供していて、入社したらどのような仕事をするのかを調べるのは当然でしょう。進学の場合も、偏差値だけでなく、志望する学部・学科でなにが学べるかを具体的に調べる必要があります。
さらに企業には、経営理念やクレド(その企業の従業員が拠りどころにする信条や行動指針)があり、それをもとに経営戦略や経営計画が立てられています。つまり、企業の方針を自分が共有できるかどうかが重要なのです。進学では、特に総合型選抜や学校推薦型選抜では、アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシーを確認しておきましょう。
経営学を活かした自己分析
また、経営学のさまざまな分析手法やツール(フレームワーク)なども、就職や進学で役立ちます。
たとえば、SWOT分析は、企業が事業方針や戦略を立てるにあたり、自社の事業の状況を、強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の4つの要素で整理して、分析する方法です。企業を自分自身に置き換えれば、自分の戦略づくり(自己分析)に活用できます。さらに、自分を「商品」と仮定して、マーケティングの手法を用いて、相手に最も訴えるアピール内容や方法を考えることができるでしょう。
経営学で学べる学問分野
経営学では、経営管理論や経営戦略論、マーケティング、ファイナンス、会計、データ処理や統計などを学びます。アントレプレナーは起業家を意味し、そのための教育や支援を行っている大学もあります。すべての学生が起業をめざすということでは必ずしもありませんが、ゼロからアイデア(事業)を創造したりリスクに挑戦したりする起業家精神はこれからの時代を自立して生きていくために非常に重要でしょう。
日本の複式簿記の始まりは福澤諭吉?【商学・会計学】
商学・会計学の目的・魅力
商取引やマーケティング、会計などを学ぶのが商学です。市場の動向や販売促進などについて研究するマーケティングや、生産者から消費者へモノの流通を設計・管理するサプライチェーン・マネジメントなど、ビジネスに関する多岐にわたるテーマが対象になります。会計学では企業等のお金の出入りや財産の状態についての計算や記録・報告などの方法を研究します。会計学科は商学部に設置されるケースがよくあります。
この記事では、企業の成績を評価するうえで身につけておきたい知識である会計について紹介します。
会計を学び企業を見る目を養う
たとえば、企業に投資するかどうか判断する場合、その企業の経営状態や財務状態を正確に把握しておく必要があります。そのため、投資家から広くお金を集めるいわゆる上場企業などは情報開示が義務付けられているほか、ホームページ等でIR(Investor Relations)情報(企業の概況、事業の状況、設備の状況、経理の状況などを記した有価証券報告書など)を公開しています。
このように、投資家やステークホルダーに対して情報を公開することは企業の責任と言えます。ちなみに、有価証券報告書(財務諸表)は誤りや虚偽記載があってはならないため公認会計士や監査法人の監査が義務付けられています。損失を隠したり、売上を水増ししたりすれば、罪に問われることになります。不正会計や粉飾決算などのニュースを耳にしたことがあるでしょう。
簿記は世界共通言語
さて、企業の成績は決算書にまとめられることになりますが、そのもととなるお金の出入りや取引などの一つひとつを記録する方法が複式簿記です。小遣い帳や家計簿などのような収支や残高を記録する単式簿記に対して、複式簿記は借方と貸方に分け、取引を原因と結果の両面から記録する方法です。複式簿記は日本においては、明治初期に福沢諭吉が「帳合之法」という本を翻訳・出版して紹介したのが始まりと言われています。
ヨーロッパにおける歴史はさらに古く、ゲーテが複式簿記を絶賛したという説もあり、その真偽はともかく、簿記は世界共通の言語とも言えるでしょう。各国の商習慣の違いはありますが、経済のグローバル化の中で、世界統一ルール(国際財務報告基準=IFRS)に近づける動きが進んでいくと思われます。
会計学で学べる学問分野
会計学では、簿記を導入として、企業外部へ報告するための財務会計、企業内部で経営の意思決定に用いる管理会計などを学びます。さらに公認会計士や税理士をめざすにあたっては税や企業に関する法律も学ぶ必要があります。専門性が高い分野ですが、会計の基礎的な知識は経営者やビジネスパーソンとして活躍する上でぜひとも身につけておきたいものです。
まとめ
イノベーション(革新や刷新、新機軸。社会に大きな変化をもたらす新しい技術・サービス・仕組みなどを生み出すこと)には、社会や経済の動向の理解やマーケティング思考が欠かせません。経済学・経営学・商学・会計学を学び、ワクワクする未来を創っていきましょう。