
執筆:八尾直輝
「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝
「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長
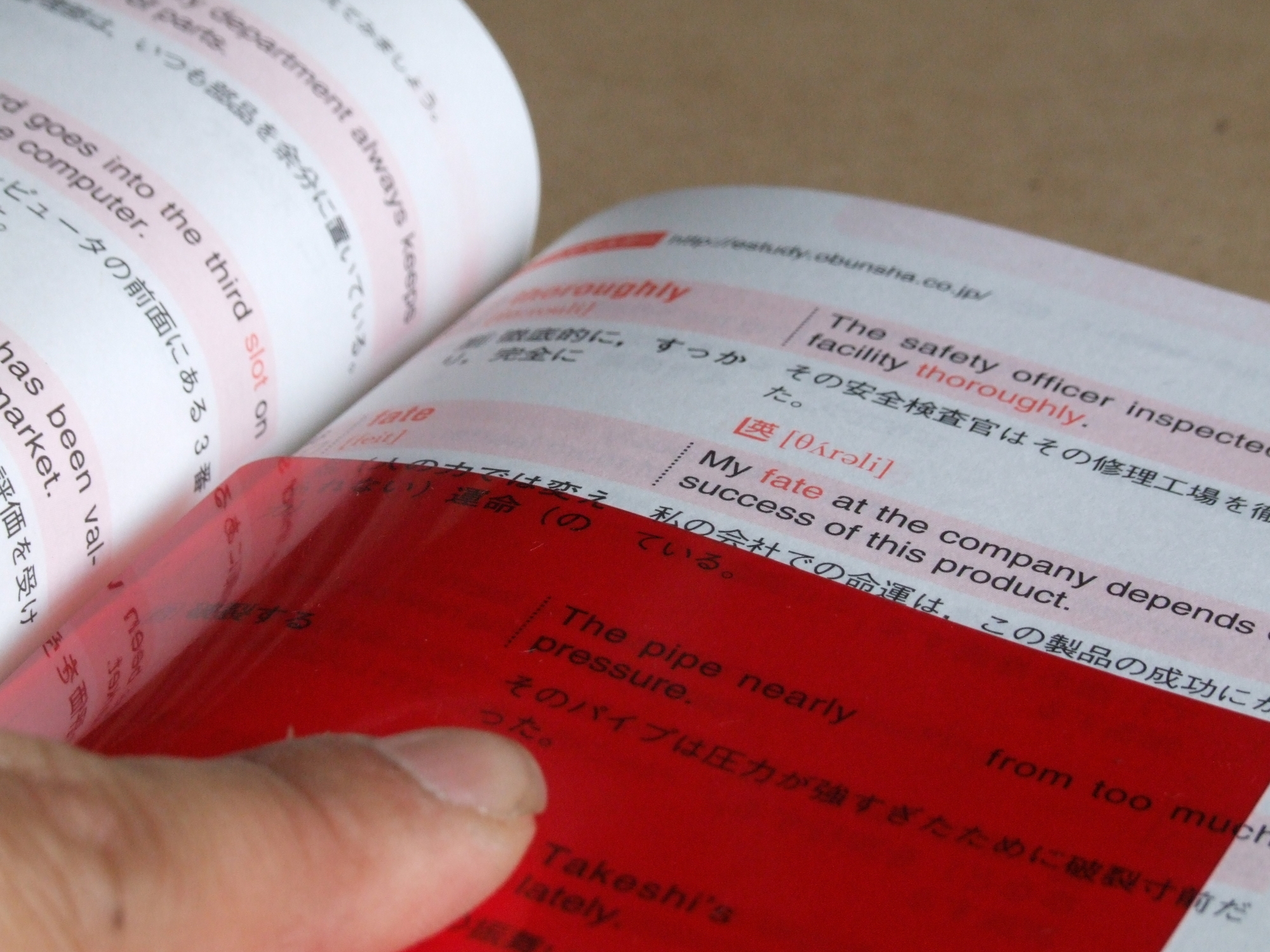
英語は、受験科目の中で避けて通ることが難しい科目です。苦手意識をなくすこと、さらなる得点力を身に着けるためには、自分に合った問題集や参考書を選び実力を着けることが必須です。自分に最適な参考書、問題集の選び方について解説します。
英語の学習は基礎が重要です。大学受験であっても、時には中学英語の復習から始めることが、合格への最短距離であることも少なくありません。
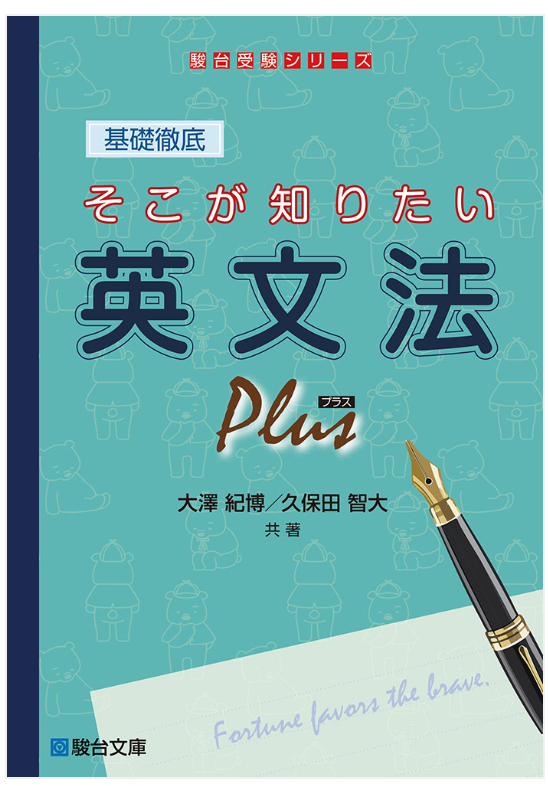
実は、高校英語を攻略するカギは「中学英語」にあります。たとえば、英文法参考書『基礎徹底 そこが知りたい英文法プラス』(駿台文庫)の目次を見てみると、第1章「時制」、第2章「助動詞」、第3章「文型」と、中学で学んだ単元がずらりと並んでいます。つまり、高校英文法の多くは、中学英語の延長線上にあるのです。
家にたとえるなら、地面や1階部分が中学英文法、2階部分が高校英語。土台がしっかりしていなければ、その上に建物を積み上げることはできません。高校英語を確実に身に着けるためにも、必要に応じて中学の内容を復習することがとても大切です。
学習法としておすすめなのは、授業で扱う単元を事前に確認し、それに関連する中学英語の内容をあらかじめ復習しておくことです。中学時代の教材が手元にあれば、予習に活用するのもよいでしょう。
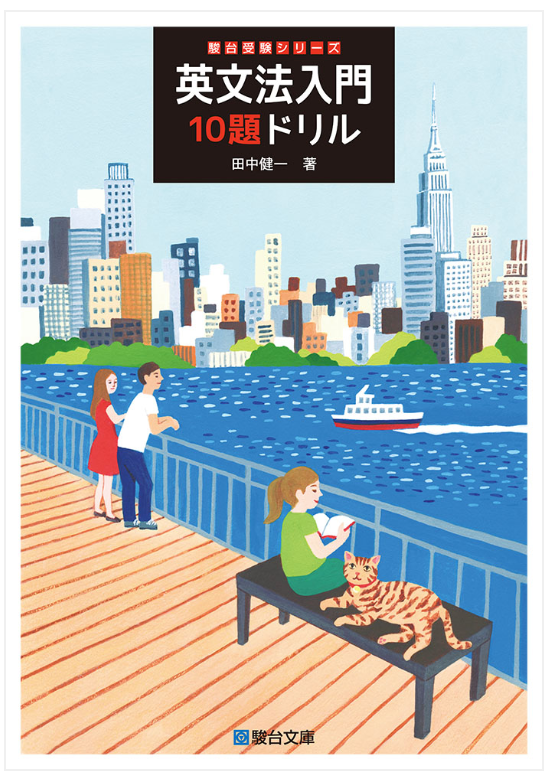
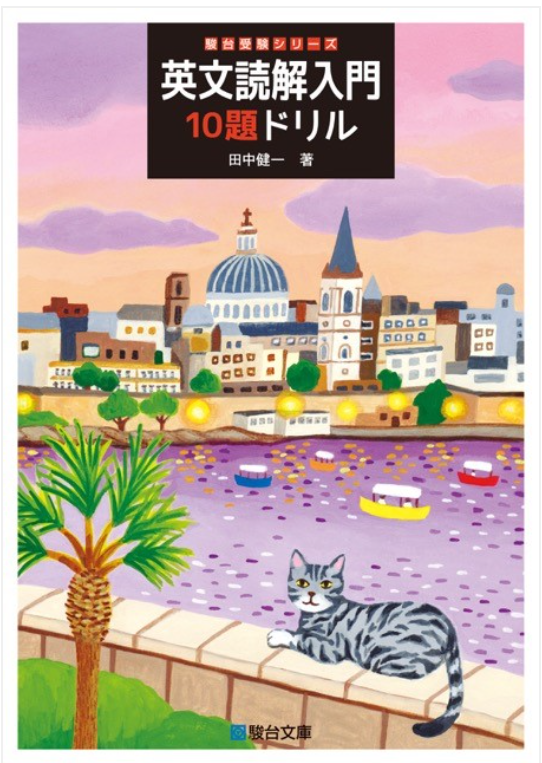
中学英語と高校英語の橋渡しをするための問題集として、『英文法入門10題ドリル』と『英文読解入門10題ドリル』(いずれも駿台文庫)がおすすめです。前者では並べ替え問題を通じて語順感覚を体得でき、後者では英文構造の理解と和訳を通じて、読解力を高めることができます。
これらの教材を効果的に使うためには、「実際に手を動かす」ことが欠かせません。読むだけでは、試験本番で知識を活かしきれないことが多いものです。ぜひ、問題集ごとにノートを1冊ずつ用意し、自分の手で解きながら学びを深めてください。
高校英語の習得は、中学英語という土台があってこそ。必要に応じて基礎に立ち返る勇気を持ち、着実に力を積み上げていきましょう。
大学入試の英語では、志望する大学や学部によって、求められる知識の深さや問題の難易度、出題傾向が異なります。ただし、どのレベルの入試であっても、「読む・書く・聞く・話す」といった基本的な英語力が必要である点は共通しています。
「難関大学を目指すから、まずは難しい問題集に取り組もう」と思いがちですが、自分の今の力に合わない教材にいきなり手を出すと、理解できずに挫折してしまうこともあります。大切なのは、自分の現状を見つめ、必要な力を段階的に積み上げていくことです。定期試験や模試の結果を振り返れば、自分の得意分野や課題が見えてきます。現在の実力を正しく把握し、無理なく着実にステップアップしていきましょう。焦らず一歩ずつ進むことが、志望校合格への最も確かな道です。
英語の対策は、高校1〜2年生の間を「基礎力養成期」、高校3年生を「実戦力養成期」と捉え、それぞれの時期に合った問題集や参考書で学ぶことが効果的です。この後の章で紹介する教材を参考にしながら、自分に合ったペースと勉強法で、着実に英語力を伸ばしていきましょう。
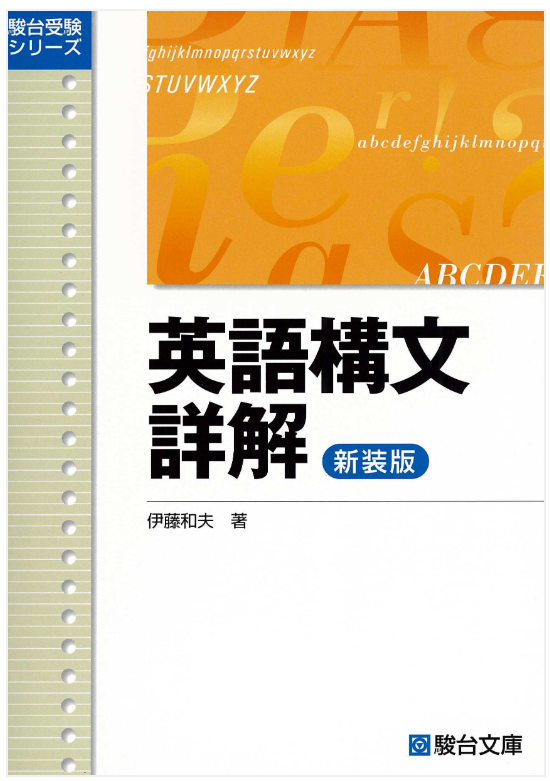
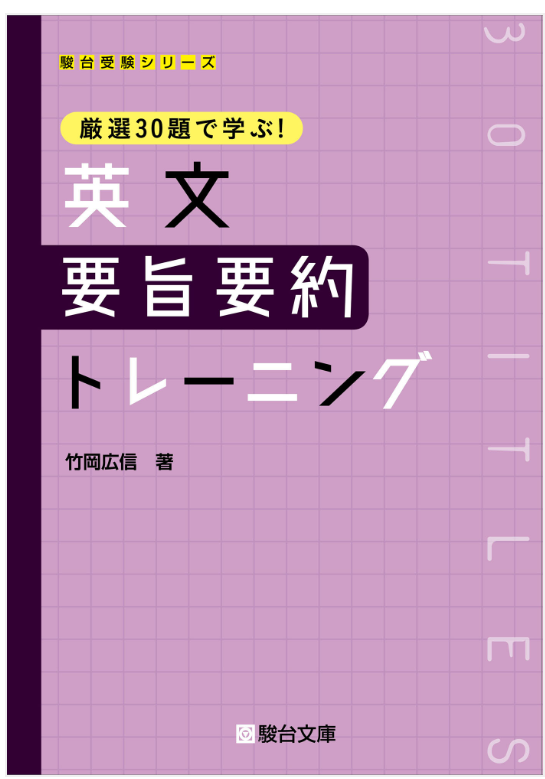
【参考書】『英語構文詳解 〈新装版〉』 【問題集】『厳選30題で学ぶ! 英文 要旨要約トレーニング』
英語の学習には参考書や問題集が欠かせません。自分にあった参考書、問題集の選び方と使い方のポイントについて解説します。
英語学習において、参考書と問題集はそれぞれ異なる役割を担っています。
参考書は、英語の知識や理解を深めるための「インプット教材」です。教科書の内容を補足しながら、文法や構文のしくみを丁寧に解説し、学習の土台を築く役割を果たします。
一方で、問題集は学んだ知識を定着させるための「アウトプット教材」です。演習を通じて理解度を確認し、応用力を高めることが主な目的です。
つまり、参考書は知識を頭に入れるために、問題集はその知識を使えるようにするために活用するものといえます。
英語力を伸ばすには、インプットとアウトプットの往復が不可欠です。
参考書と問題集をうまく使い分けながら、確かな英語力を身につけていきましょう。
参考書や問題集を選ぶとき、「友達が使っているから」「ネットで評判がいいから」といった理由で選んでいませんか?確かに人気のある教材には理由がありますが、それが自分にとって最適とは限りません。
自分に本当に合った教材を選ぶためには、「現状の英語力」と「目指すレベル」の両方を意識することが大切です。その際の目安として、これまで受けてきた模試の偏差値を活用するのが有効です。ここでは、ベネッセ・駿台模試を基準に、長文読解におすすめの教材をレベル別に紹介します。
【入門】
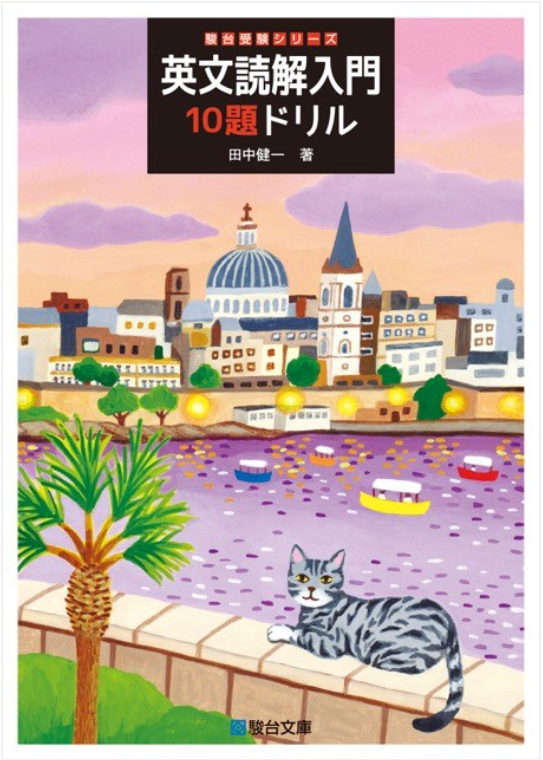
『英文読解入門10題ドリル』は、英文読解の基礎から丁寧に学べる一冊です。第1章では基本文型の理解、第2章では句や節が主語になる文の正確な読み取り、第3章では総合問題を通じた実戦練習と、段階的に力をつけていく構成になっています。語注も豊富なので、語彙に不安がある人でも安心して取り組めます。
【基礎】
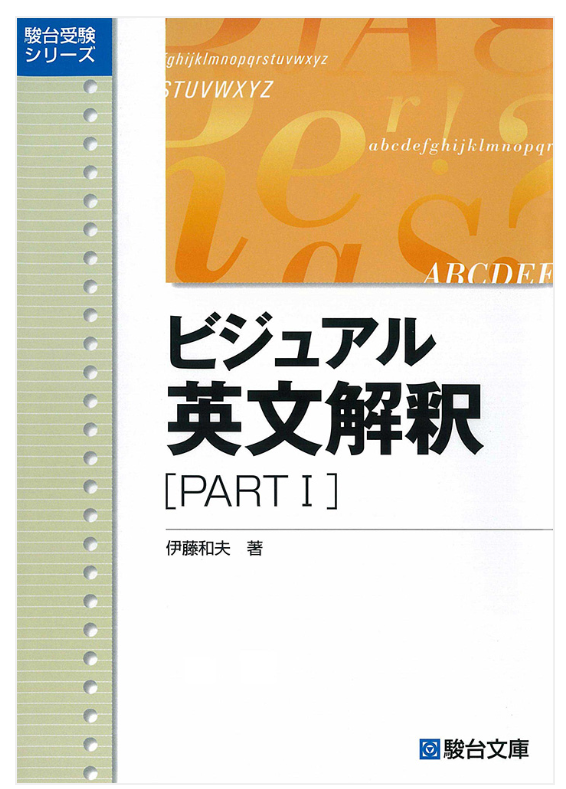
『ビジュアル英文解釈 PARTⅠ』は、講義形式で読み進めるスタイル。主語の見つけ方や意味上の主語の扱いなど、読解の基礎技術を文法解説+演習+復習という流れでしっかり学べます。「ウィンストン・チャーチルと犬」「人口増加と食糧問題」など興味深い題材が多く、楽しみながら読み方の型を習得できます。
さらに発展的な英文に挑戦したい人は、『ビジュアル英文解釈 PARTⅡ』にもぜひ取り組んでください。
【中級~】
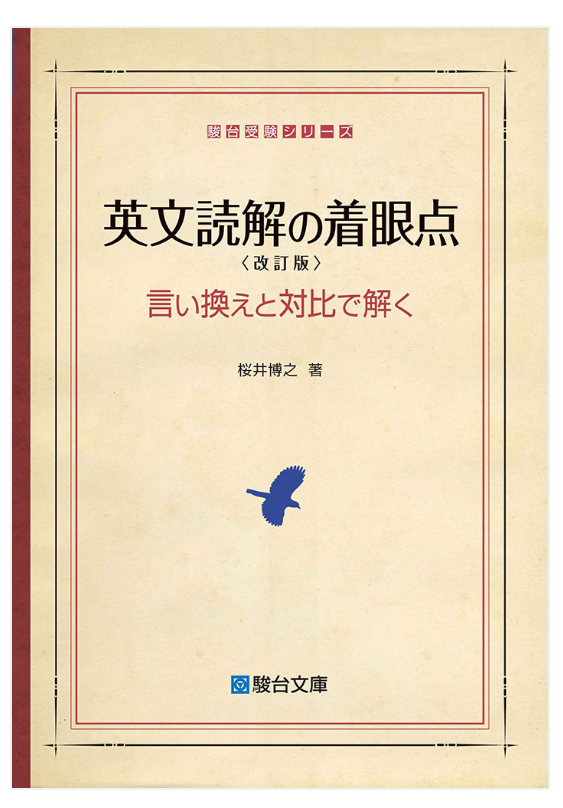
『英文読解の着眼点〈改訂版〉-言い換えと対比で解く-』は、長文読解に必要な「言い換え」「対比」「因果」といった論理的関係を見抜く力を養う教材です。PartⅠで英文の構造やつながりの基本原則を学び、PartⅡで実戦的な演習に挑戦。さらに別冊には、構造を視覚的に整理した「英文見取り図」があり、読み方の技術を実際の問題に活かす練習ができます。
大切なのは、無理なく続けられる教材を選び、日々の積み重ねを大切にすることです。自分の成長を実感できるような一冊に出会えると、英語学習はぐっと楽しくなりますよ。

大学受験に向けた学習では、問題集を「とにかくたくさん解く」だけでは、効率的に学力を伸ばすことはできません。同じ一冊でも、使い方を工夫することで得られる成果は大きく変わります。ここでは、受験生にとって特に重要な2つのポイントをご紹介します。
「参考書と問題集 目的に合わせて選ぶ」でも紹介した通り、問題集はアウトプット(知識を使う)ための道具、参考書はインプット(知識を得る)ための道具です。一方に偏った学習では、理解が浅くなったり、応用力が身につかなかったりする原因になります。
問題を解く中で出てきた疑問やあいまいな知識は、その都度参考書に戻って確認しましょう。
たとえば、『英文和訳の着眼点 タテとヨコの意識づけ』第2問に登場する “act in a manner quite different from that in which each individual…” という英文に取り組んだとき、
「in which 以降の意味は何となく取れるけれど、『前置詞+関係代名詞』という構造が正確に理解できていないかもしれない」
と感じたとします。そのようなときには、英文法の問題集『基礎徹底 そこが知りたい英文法プラス』(駿台文庫)の目次を確認し、該当の項目―Lesson 48「関係題名詞(5)」―を開いて復習するとよいでしょう。このように問題集と参考書を効果的に併用することで、疑問点が放置されることなく、次の学びにつなげることができます。
「アウトプット(問題集を解く)→インプット(参考書で確認)→再アウトプット(もう一度解く)」という学習サイクルを意識することで、知識の定着が促され、理解も深まります。単なる答え合わせで終わらせず、「なぜ間違えたのか」「どこで考え違いをしたのか」を振り返ることが、合格への確かな一歩となります。
どれだけ丁寧に問題演習を実施したとしても、一度解いただけで知識が定着することはありません。間違えた問題は必ず時間を空けて解き直し、「思い出す」プロセスを通して記憶を定着させましょう。
そのためにも、問題集に直接書き込まず、解答はノートに記録するのがおすすめです。解説欄にメモを取るのは問題ありませんが、問題のページには答えやヒントを書き込まないように注意してください。書き込みがあると、解き直しの効果が薄れてしまいます。
また、間違えた問題を可視化する工夫も大切です。おすすめは、問題の横に「正」の字を記入して、間違えた回数を管理する方法。一目で弱点がわかり、復習すべき箇所が明確になります。
英語力を伸ばすうえで、日々のインプットの積み重ねは欠かせません。しかし、部活動や学校行事に追われる高校生活のなかで、まとまった学習時間を確保するのは容易ではありません。そこで鍵となるのが、すきま時間の活用です
とりわけ、通学中や待ち時間といった机のない環境では、音声を活用した学習が非常に有効です。たとえば『英作文 基本300選〈5訂版〉』のように、スマートフォンで英文音声を再生できる教材、参考書を用いることで、移動時間をそのまま英語学習の時間へと転換することが可能になります。
例えばその日に学習した内容を、帰り道に復習するのがおすすめです。自習室で英文の意味と構造を理解し、その後の移動中に音声を聴きながら、一文ごとに一時停止して内容を頭の中で再現するのがいいでしょう。もし可能であれば、音声の後に実際に声に出して文を発音するとより効果的です。英文を再現できなかった箇所があれば、帰宅後にすぐ復習することで、より深い理解と定着が期待できます。
学習の成果は、必ずしも机に向かった時間の長さだけで測られるものではありません。このように音声学習を習慣化することで、リスニング力はもちろん、文法や英作文の力も自然と養われていきます。
英語は自分の強化したいスキルを的確に強化することが効率的な学習につながります。ここでは、スキル別におすすめの参考書と、その使い方について解説します。
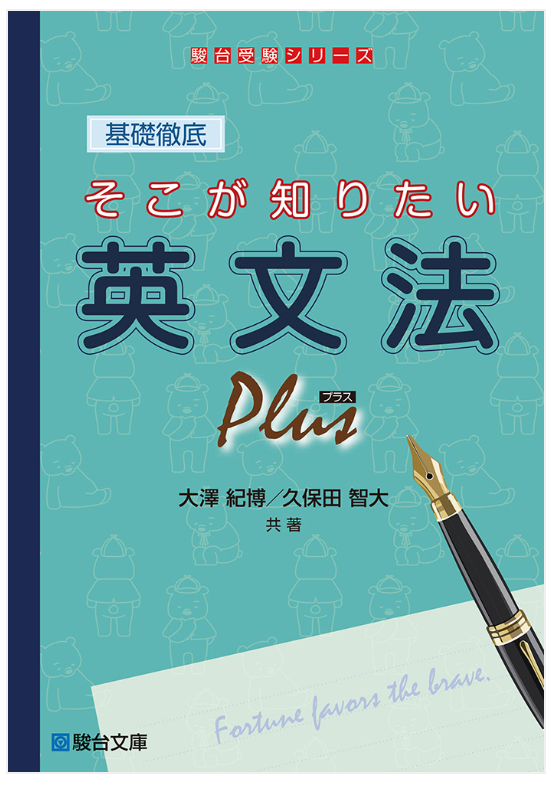
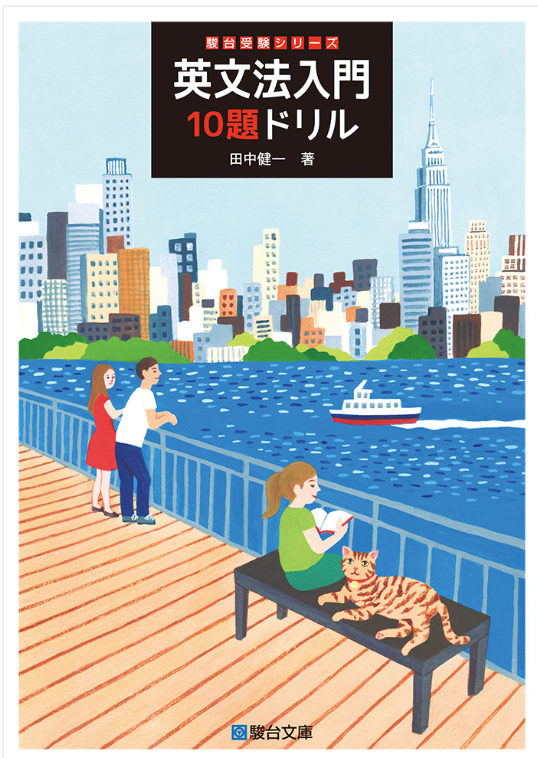
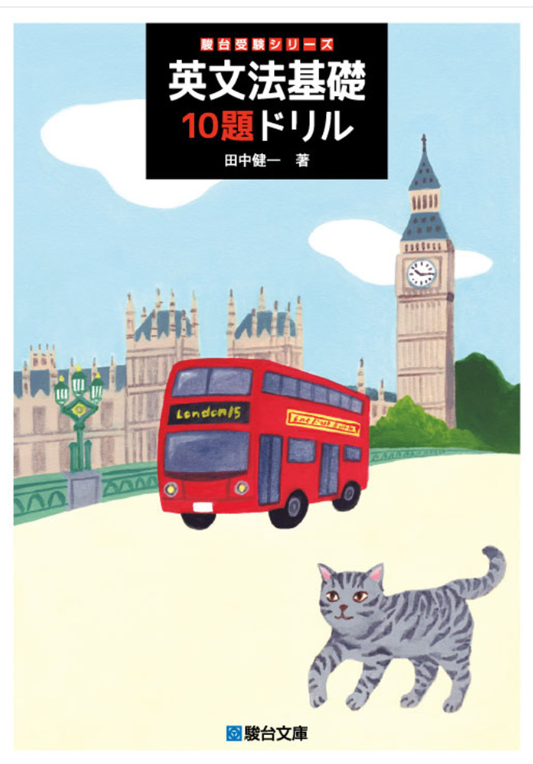
『基礎徹底 そこが知りたい英文法プラス』『英文法入門10題ドリル』 『英文法基礎10題ドリル』
これから英語を得意科目にしていきたいと考えている人は、まずは文法のインプットから始めてみましょう。英文法の知識は、文法問題だけでなく、長文読解・英作文・リスニングを含むあらゆる設問の基盤となるからです。
英文法の基礎知識を身に着けるためのおすすめの参考書として『基礎徹底 そこが知りたい英文法プラス』があります。全11章・72レッスンで高校英文法を体系的に学ぶことができ、例題や練習問題も豊富に収録されています。授業の進度に合わせて、必要な箇所から学習を進めてもよいでしょう。
また、別冊には「品詞」「文の要素」「修飾語」など、文法の基本に関する解説も収録されており、理解があいまいなときには活用できます。
『英文法入門10題ドリル』および『英文法基礎10題ドリル』の2冊は、各講に文法解説・例文・演習問題がセットになっており、英文法の基本的な型を段階的に習得できます。取り組む際は、まず講義ページの文法解説を読み、5つの例文をしっかり押さえたしたうえで、EXERCISES A・Bに進むのが効果的です。
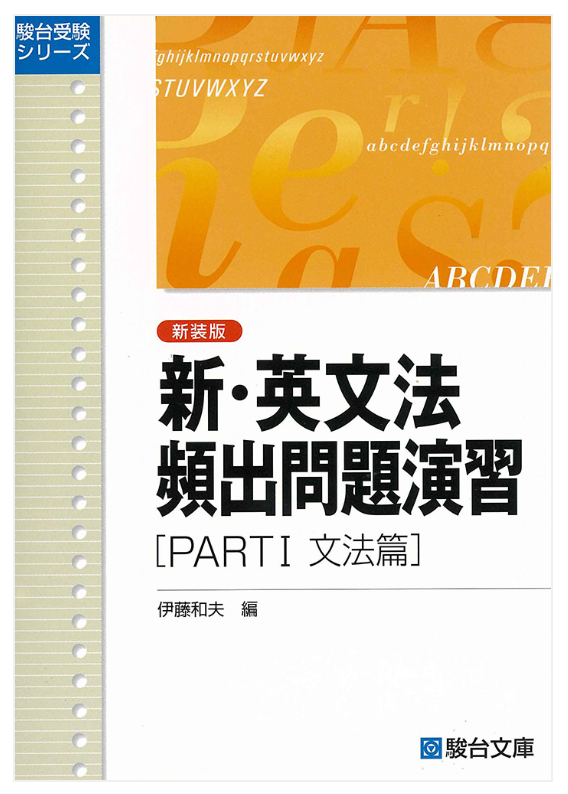
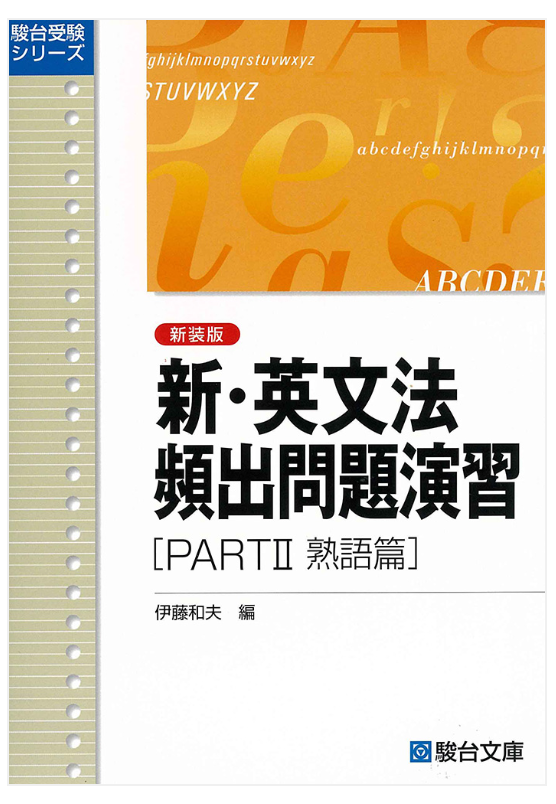
『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅠ 文法篇』 『新・英文法頻出問題演習 〈新装版〉PARTⅡ 熟語篇』
基礎の学習を一通り終え、さらに実戦的な演習に進みたい人には、『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅠ 文法篇』『新・英文法頻出問題演習 〈新装版〉PARTⅡ 熟語篇』をおすすめします。空所補充、語順整序、書き換えなど、大学入試で頻出の形式に幅広く対応しており、すべての問題に丁寧な文法のポイント解説がついています。正解した問題も含め、必ずすべての解説に目を通すようにしましょう。理解の深まり方が大きく変わってきます。
また、演習中に疑問点が生じたときは、そのままにせず、信頼できる参考書で確認することも大切です。『基礎徹底 そこが知りたい英文法プラス』に立ち戻り、調べた内容をノートにまとめておけば、復習の際にも大いに役立ちます。
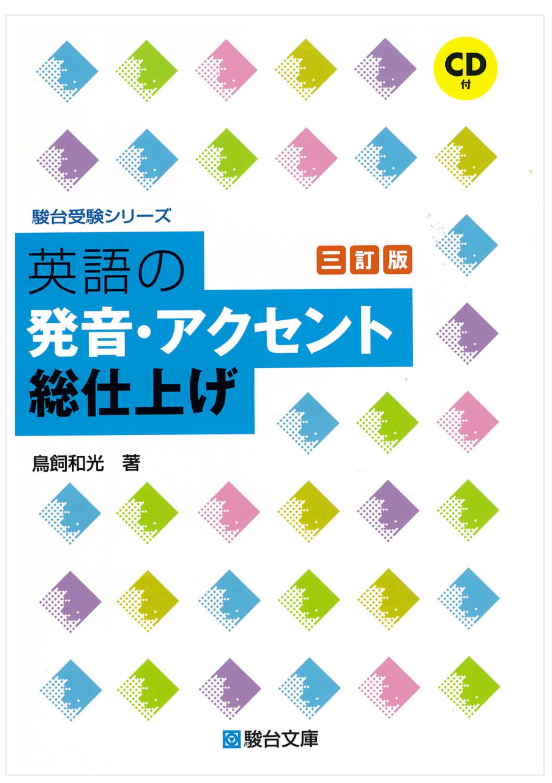
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)では、かつての大学入試センター試験で見られた発音・アクセントの単独問題が出題されなくなりました。そのため、「もう発音やアクセントは勉強しなくてもいいのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、英単語の暗記やリスニング力の向上を目指すうえで、発音・アクセントのルールを理解しておくことは、今でも非常に重要です。正しい発音をイメージできることで、単語の記憶が定着しやすくなり、英語を聞き取る力も自然と伸びていきます。英語を得意科目にしたいと考えている人ほど、しっかり学んでおきたい分野です。
発音・アクセントの学習におすすめの参考書は『英語の発音・アクセント総仕上げ〈三訂版〉』です。「発音編」と「アクセント編」に分かれており、受験生がつまずきやすいポイントを丁寧に解説しています。付属のCD音声を繰り返し聞きながら、自分でも声に出してまねることで、発音とアクセントのルールを体で覚えることができます。学習効果を高めるためには、短期集中で取り組むのが効果的です。学期中は時間が取りづらいという人も、ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休暇を利用し、「この1週間でやりきる」といった目標を立てて取り組んでみてください。
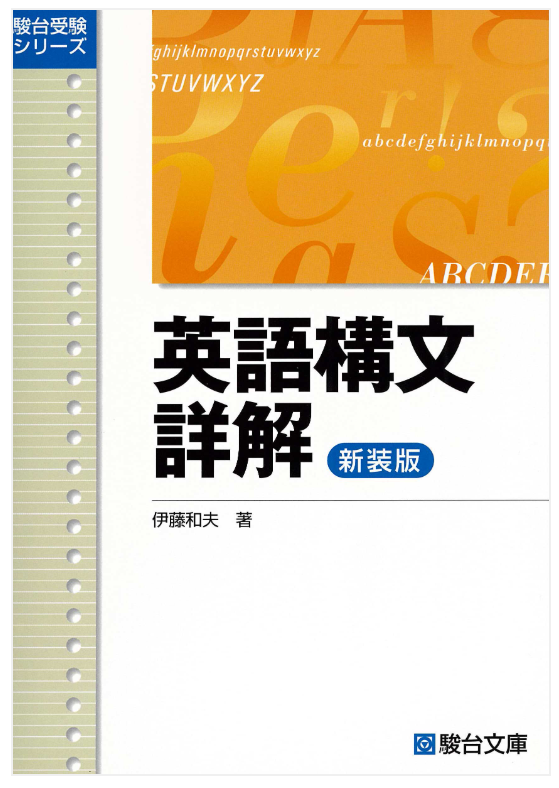
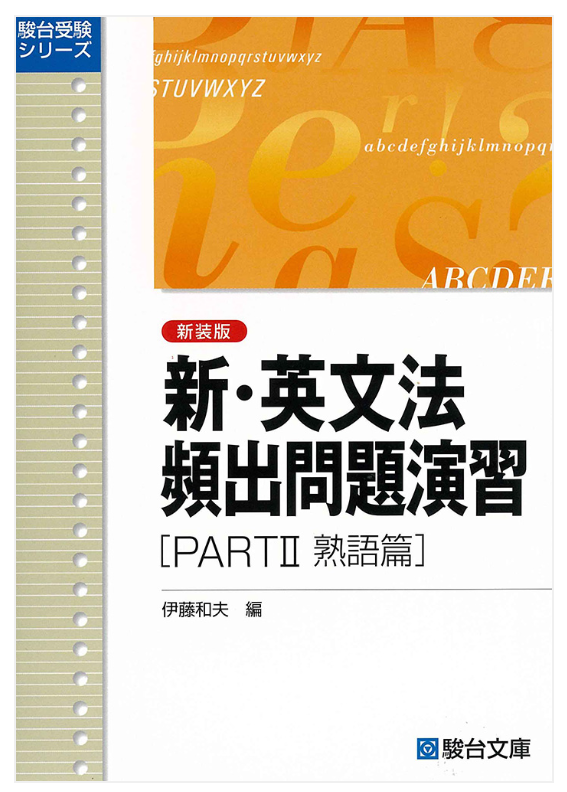
『英語構文詳解〈新装版〉』 『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅡ 熟語篇』
さらに、長文読解や英作文の得点力を高めるためには、構文やイディオムの理解も欠かせません。構文の学習には『英語構文詳解〈新装版〉』がおすすめです。特にChapter1〜4では、文の基本構造(主語・目的語・補語・動詞句)を詳しく学ぶことができ、学校や塾での授業と並行して取り組むことで理解が一層深まります。
一方、イディオムの習得には『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅡ 熟語篇』が有効です。「動詞+前置詞」「動詞+目的語+[前置詞]」といった形で熟語がタイプ別に整理されているため、知識を体系的に身に着けることができます。各パートは約20ページ程度で構成されており、1日1パートのペースで取り組めば、1週間ほどで全体を終えることも十分可能です。こちらも長期休暇を利用して、一気に学習を進めるスタイルがおすすめです。
大学入試の英語では、長文読解が最も高い配点を占めることが多くあります。入試の難度が上がるほど、文法や語彙の知識だけでは太刀打ちできなくなり、英文を論理的に、そして素早く読み解く力が求められます。そのためには、一文一文を正確に読み取る「精読」力と、文脈の流れをとらえて英文の全体像を素早く把握する「速読」力の両方をバランスよく鍛えることが必要です。これらの力を効率よく身に着けるためにも、目的に応じた問題集を選ぶことが重要です。
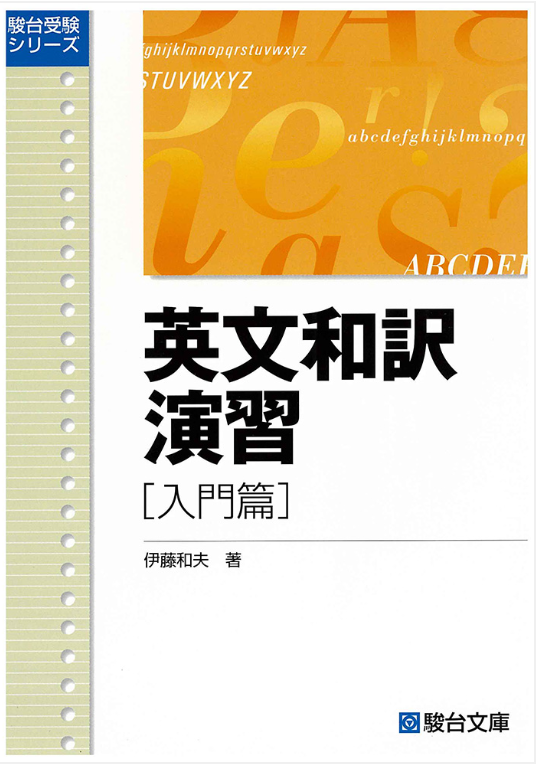
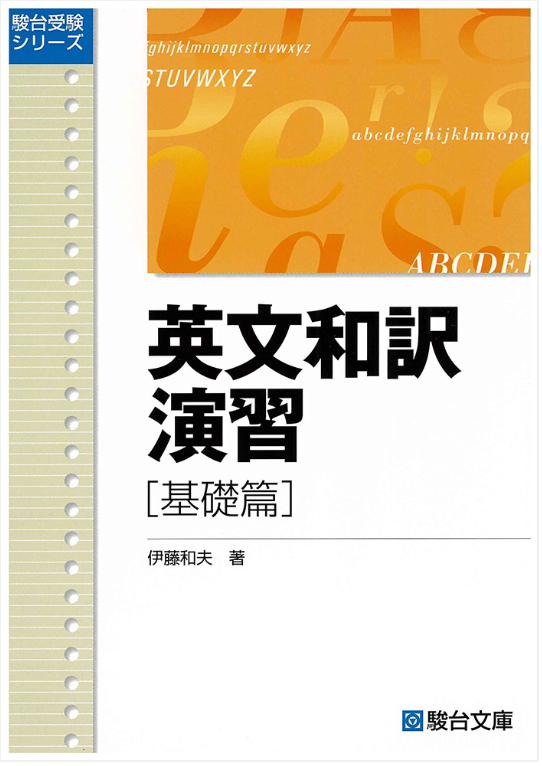
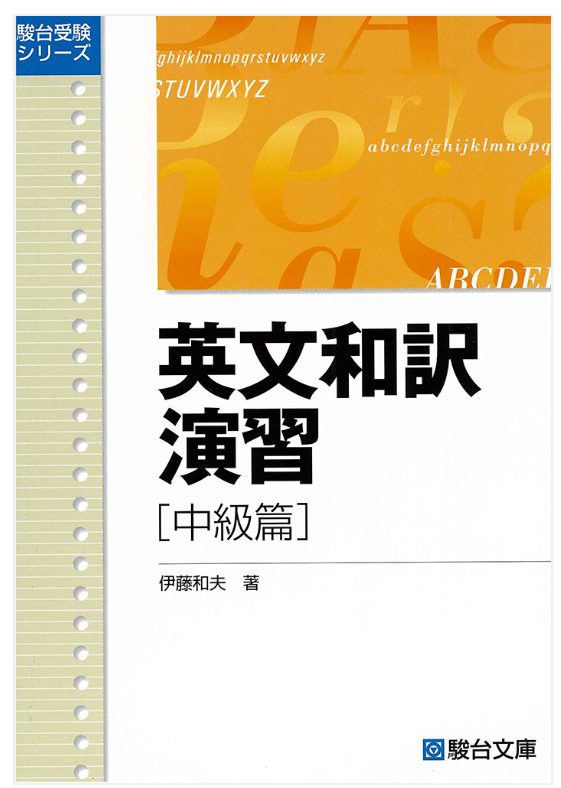
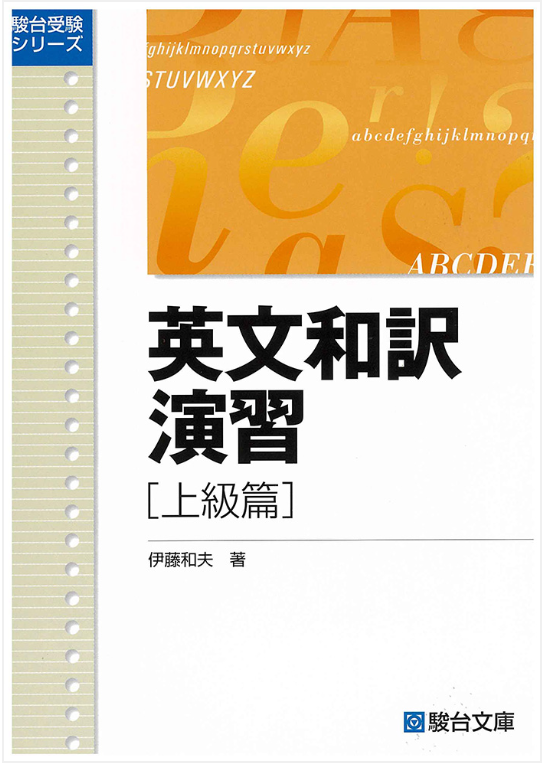
まず、「精読」力の土台を築くのに適した教材が、『英文和訳演習』シリーズです。構文を正確に把握しながら、英文を日本語に訳すプロセスを通じて、文の構造や意味を丁寧に読み解く力が養われます。このシリーズは入門篇・基礎篇・中級篇・上級篇の4段階で構成されており、現状の実力に応じて無理なくステップアップしながら取り組むことができます。まずは入門篇や基礎篇で基本的な構文の読み取り方を身につけ、その後に目標とするレベルに応じて中級篇・上級篇へと進むことで、より複雑な英文にも対応できる力を養成できます。特に難関大学を志望する受験生にとっては、論理的な思考力と表現力の両方を高めるトレーニングとして非常に有効です。設問を解くだけでなく、模範訳と自分の訳を比較しながら復習することで、英文理解の精度が格段に向上します。
一方で、「速読」力や論理的読解力を鍛えたい人におすすめなのが、『英文読解の着眼点〈改訂版〉―言い換えと対比で解く―』です。この問題集は、PartⅠ「読み方・解き方の基本」とPartⅡ「問題演習」の二部構成。PartⅠでは「パラグラフのまとまり」や「文と文のつながり」など、論理的に英文を読むための視点を学びます。PartⅡでは、20題の良問を通して実戦的な読解力を養います。さらに別冊「英文見取り図編」では、本文中の言い換え・対比・因果関係に印がつけられており、文構造を視覚的に捉える練習も可能です。時間制限のある試験本番で、情報を効率よく整理して読み取る力を高めたい人にはぴったりの一冊です。
英語の4技能を伸ばすためには、適切に参考書を選ぶことも重要ですが、その学び方がより重要と言えます。
例えば、リスニングやスピーキングの力を伸ばすためには、単語や文法の学習のときに、発音を調べたり実際に声に出してみたりすることが重要です。
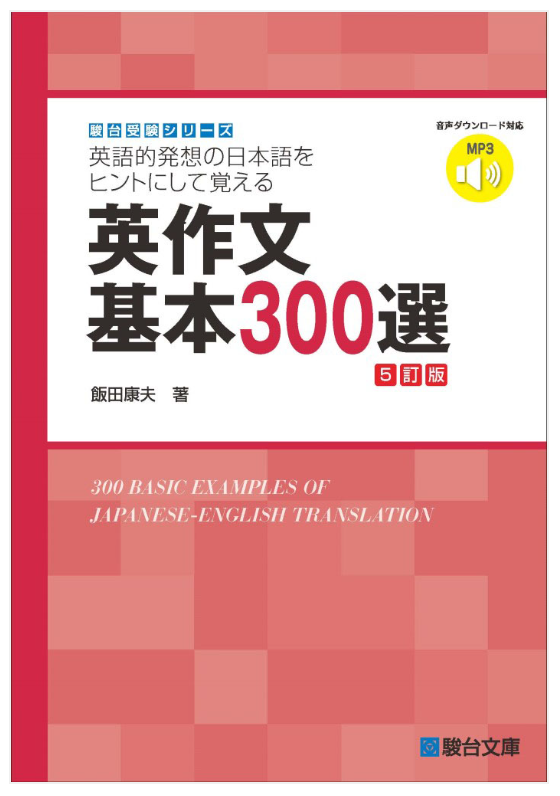
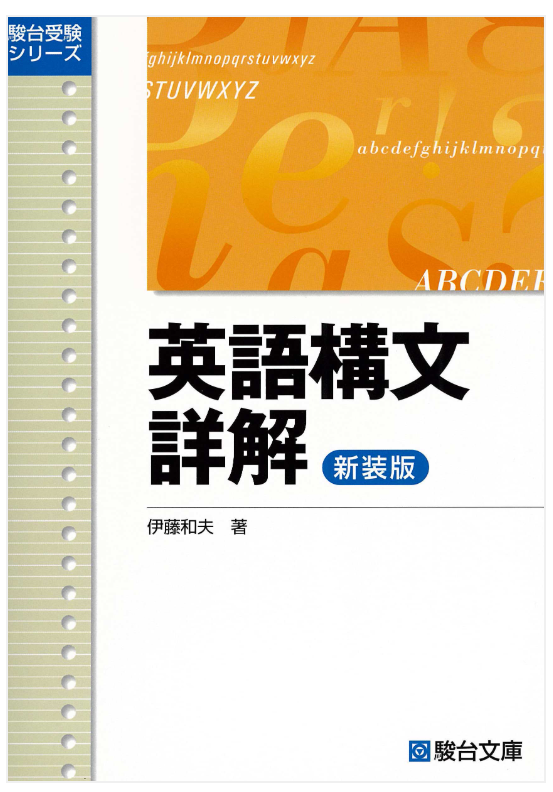
『英作文 基本300選〈5訂版〉』『英語構文詳解〈新装版〉』
「リーディング力を強化したくて、毎日長文を読んでいるのに成績が伸びない…。」こうした悩みを抱える受験生は少なくありません。たしかに、英文を読む量を増やすことは大切ですが、それだけでリーディング力が伸びるとは限りません。
見落とされがちなのは、英文を正確に読みこなすためには、それ以前に語彙力や文法力といった基礎知識がしっかり備わっている必要がある点です。基礎的な知識が不十分なまま長文を読んでいても、内容の理解が曖昧になり、読解の精度も上がりません。もし「頑張っているのに伸びない」と感じているなら、一度立ち止まり、語彙や文法の理解に抜けがないかを見直してみましょう。
特に英文法については、「4択問題が解けるから大丈夫」と安心してしまう人が少なくありません。しかし、文法の知識を実際の英文中で活用できてこそ、本当の意味で「使える文法力」と言えます。「英文法をマスターするための参考書」で取り上げた問題集や参考書の演習・復習を通じて、土台となる知識の定着と運用力の強化を図っていきましょう。
また、英語特有の構文パターンに慣れておくことも、読解力の底上げには欠かせません。長文読解でつまずく原因の多くは、構文の取り方がわからず、文の骨組みが見えなくなってしまうことにあります。『英作文 基本300選〈5訂版〉』や『英語構文詳解〈新装版〉』は、重要構文を体系的に学べる良書です。1日1構文ずつでも継続して学ぶことで、「英文を読むための目」が確実に育ちます。
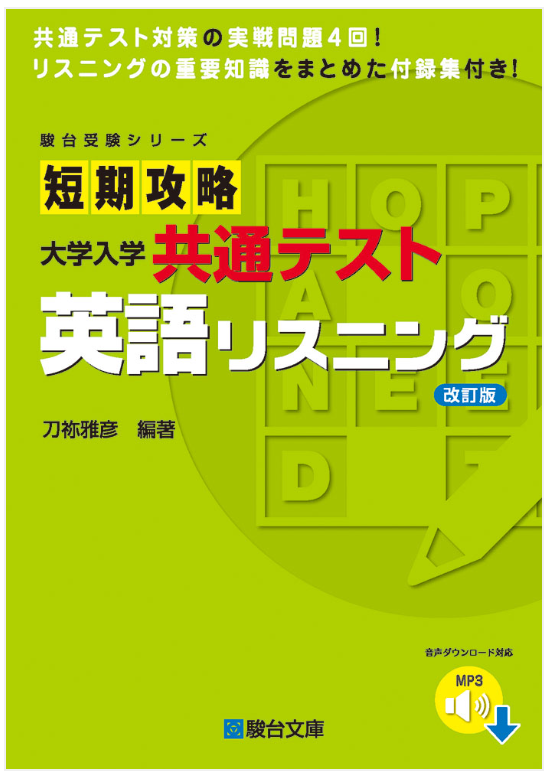
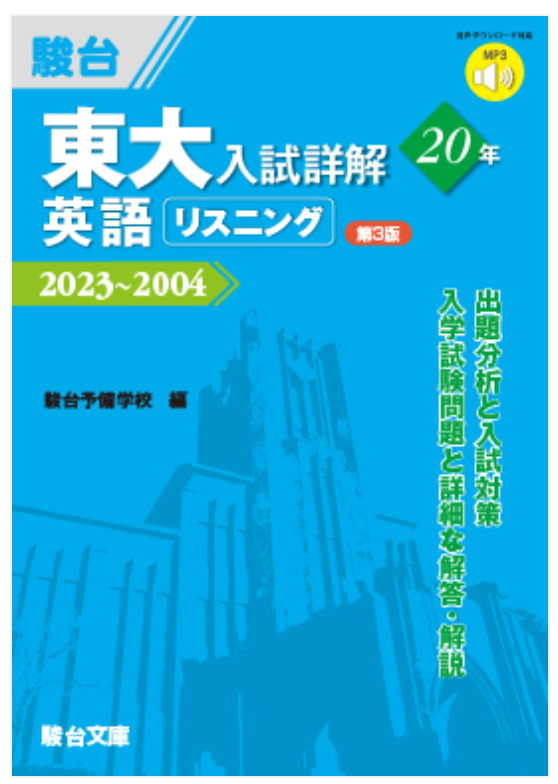
『短期攻略 大学入学共通テスト 英語リスニング〈改訂版〉』 『東大入試詳解20年 英語リスニング』
共通テストをはじめ、国公立大学の二次試験や英検など、多くの入試でリスニング問題が出題されます。志望校合格を目指すうえで、リスニング力の向上は避けて通れない課題です。しかし、リーディングやライティングと比べて対策が後回しにされがちで、「高3になってから焦って始めたものの、結局思うように点数が伸びなかった」というケースも少なくありません。リスニング力は一朝一夕では身につかないため、早い段階から継続的に取り組むことが何より大切です。
リスニング力を伸ばすには、「英語を聞き取る力」と「聞いた内容をもとに正しく解答する力」の両方を意識する必要があります。高校1~2年生のうちは、まず「聞き取る力」の土台を作ることを目標にしましょう。具体的には、普段使用している単語帳や長文問題、英作文集に付属している音声を活用し、毎日少しずつでも英語を耳にする習慣を着けることが効果的です。たとえば、学校や塾で扱った英文の音声を1題につき10回程度繰り返し聞くだけでも、数か月後には明らかな成長を実感できるはずです。
高校3年生からは、「問題を解く力」の養成に本格的に取り組みましょう。ここからは実際の試験形式に慣れることが重要です。共通テスト対策には『短期攻略 大学入学共通テスト 英語リスニング〈改訂版〉』、東京大学を志望する場合には『東大入試詳解20年 英語リスニング』など、レベルや形式に応じた問題集を活用するとよいでしょう。これらの参考書は、模試を一つの目標としてスケジュールを立て、たとえば「模試の1か月前から演習を開始する」といった形で計画的に取り組むことで、より効果的に力を伸ばすことができます。
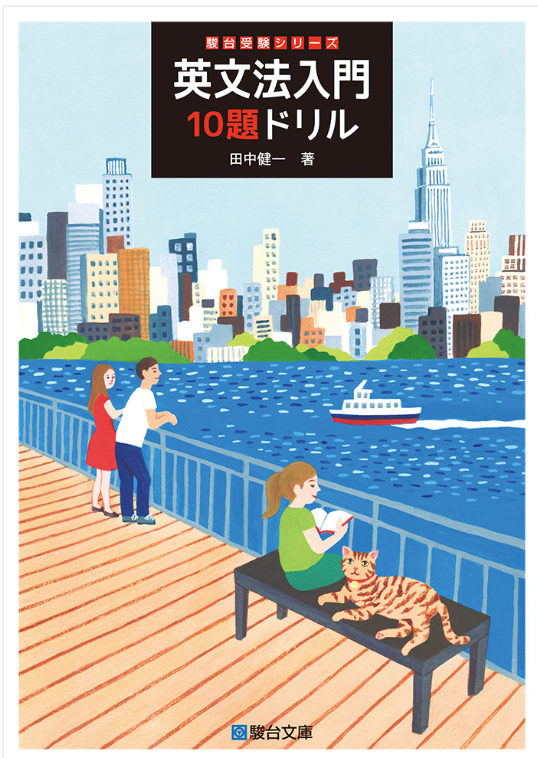
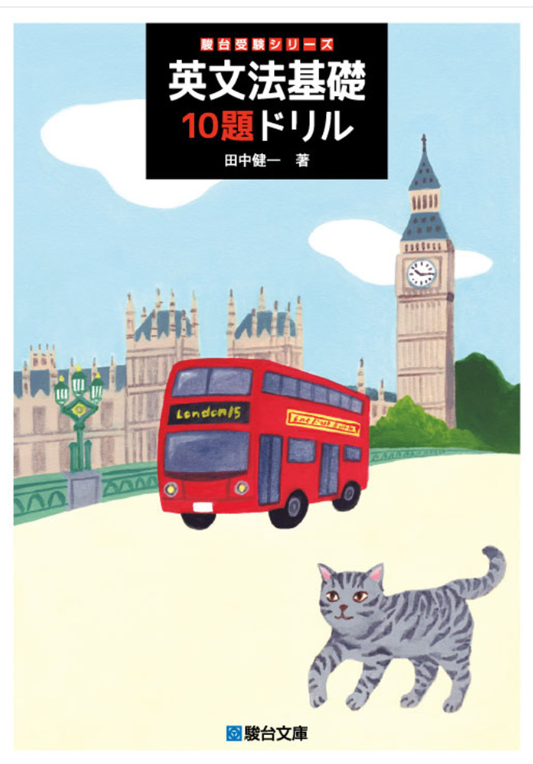
近年、英検をはじめとした英語外部試験を活用する大学入試が増えており、スピーキング力の重要性がますます高まっています。スピーキング対策というと「特別な練習が必要」と構えてしまいがちですが、実は日頃の英文法学習の中にも効果的に組み込むことが可能です。
たとえば『英文法入門10題ドリル』『英文法基礎10題ドリル』のような文法問題集を使う際、解説ページにある例文を繰り返し音読し、「思い出すまでもなく口をついて出てくる」状態にすることで、スピーキングの土台を自然と鍛えることができます。冠詞や前置詞、基本の文型など、会話に欠かせない要素が網羅されているため、効率よく力を伸ばすことができるでしょう。
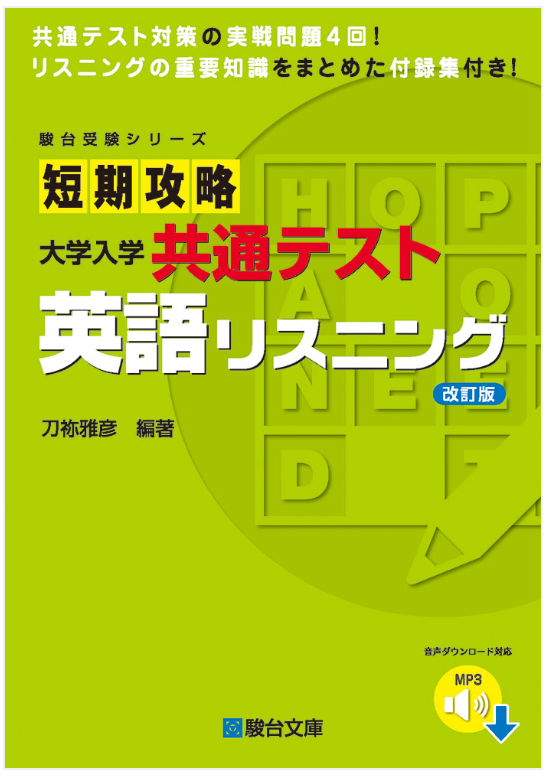
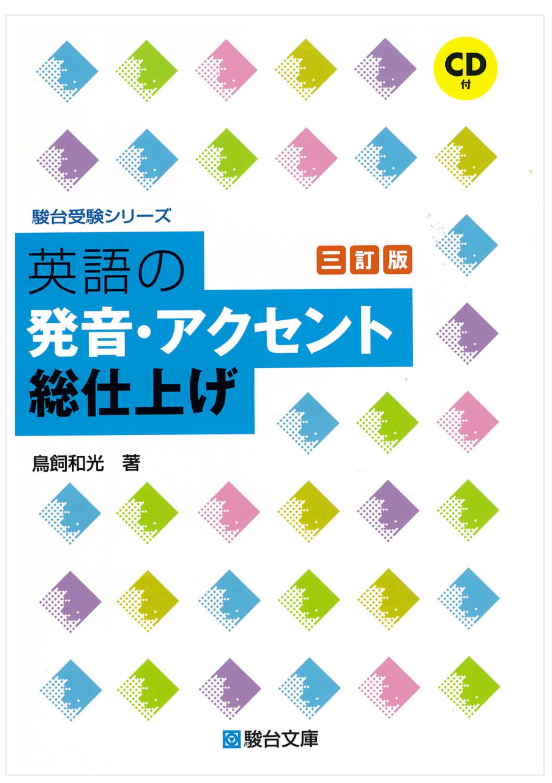
『短期攻略 大学入学共通テスト 英語リスニング 改訂版』 『英語の発音・アクセント総仕上げ〈三訂版〉』
また、共通テストのリスニング問題、特に対話型問題に出てくる表現をそっくりそのまま覚えてしまうのも実戦的なトレーニングです。『短期攻略 大学入学共通テスト 英語リスニング 改訂版』などのリスニング問題集を活用し、「聞いて、リピートする」練習を習慣にしていくと、発話の自然さや反応の速さが身に着きます。
さらに発音やアクセントをより本格的に学びたい場合は、『英語の発音・アクセント総仕上げ〈三訂版〉』がおすすめです。正しい音のイメージを持つことで、スピーキングだけでなくリスニング力も飛躍的に向上します。
スピーキング力は日々の学習の工夫次第で着実に伸ばせます。ぜひ、普段の勉強に「声に出す」ことを意識して取り入れてみてください。
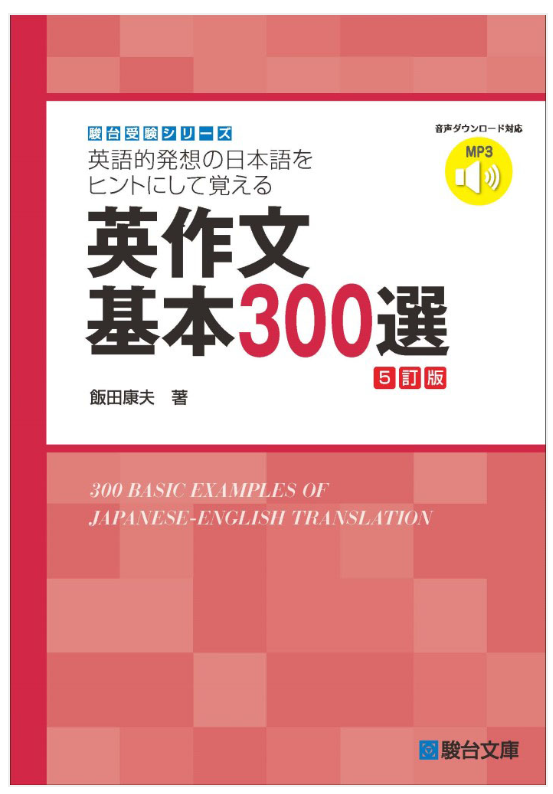
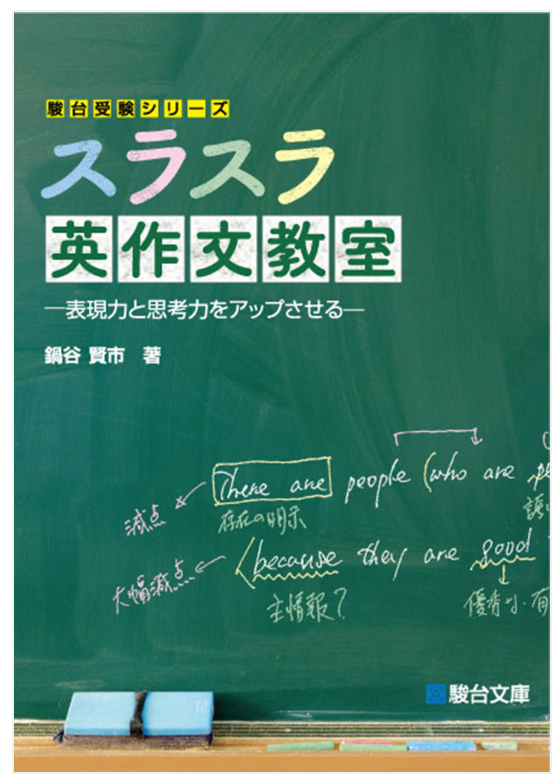
大学入試の英作文対策では、「何から手をつければよいか分からない」という声をよく耳にします。英作文の力を段階的に伸ばすためには、学習を大きく2つのステップに分けて取り組むことが大切です。第1段階は「基本例文を覚えること」、第2段階は「覚えた例文を応用すること」です。
まず、第1段階でぜひ取り組んでほしいのが『英作文 基本300選〈5訂版〉』です。この参考書には、大学入試で頻出の重要構文が300文厳選されており、それぞれに丁寧な文法解説が付されています。単なる暗記ではなく、「なぜその表現を使うのか」「どのような場面で使えるのか」といった理解を深めながら学べるのが特徴です。例文を何度も書き写し、音読し、語順を口になじませることで、英語の型が自然と定着していきます。また、巻末に収録されている「英文法道場」では、「there is構文」や「クジラ構文」など、受験生がつまずきやすい文法項目がコンパクトにまとめられており、すきま時間の学習にも最適です。
次のステップとしておすすめしたいのが、『スラスラ英作文教室』です。この参考書では、英作文の「答案作成のプロセス」が非常に詳しく解説されています。PartⅠでは、問題の読み取りから語句の選定、文全体の構成に至るまでを段階的に示しており、「例文は覚えたけれど、実際の問題ではどう書けばよいのか分からない」といった悩みに正面から応えてくれます。さらに、PartⅡでは、因果関係・対比・譲歩・言い換えといった論理展開を支える表現が豊富に紹介されており、過去問演習後の振り返りや表現力の強化にも大いに役立ちます。
共通テストは、国公立大学の入試に必要なのはもちろんのこと、私立大学でも共通テスト利用入試を取り入れているところが多く、得点次第で選択肢が大きく広がります。受験を有利に進めるためにも、高得点を狙って対策に取り組んでおきたいところです。
ただし、いきなり過去問や模試を解き始めても、なかなか思うように点数が伸びないことがあります。まずは問題集・参考書を使って、語彙・文法・読解といった基本的な知識をきちんと身につけておくことが重要です。とくに高校2年生までの時期は、基礎力を固める絶好のタイミングですので、これまで紹介してきたスキル別・4技能別の問題集を活用しながら、丁寧に積み重ねていきましょう。
今回は共通テストの中でも、対策方法がつかみにくいリスニングに焦点を当てて、おすすめの問題集を紹介します。『短期攻略 大学入学共通テスト 英語リスニング〈改訂版〉』は、共通テストの出題形式に即した実戦問題が4回分収録されており、対話・ビジュアル・講義形式などの出題パターンに対応できます。加えて、音声の聞き取りポイントや、頻出表現のまとめも掲載されており、短期間で効率よく実力を伸ばしたい人にぴったりの一冊です。問題を解くだけで終わらせるのではなく、必ず解説にもじっくり目を通しましょう。正解・不正解にかかわらず、解説から「なぜその答えになるのか」「どんな視点で解けばよいのか」といった考え方を学ぶことで、初見の問題にも応用できる力が身に着きます。
英語は大学ごとに出題傾向が様々です。英作文の有無を把握することや、特徴的な出題をあらかじめ対策しておくことが、合格するために必要なのです。ここでは、大学ごとにおすすめの参考書を見ていきます。
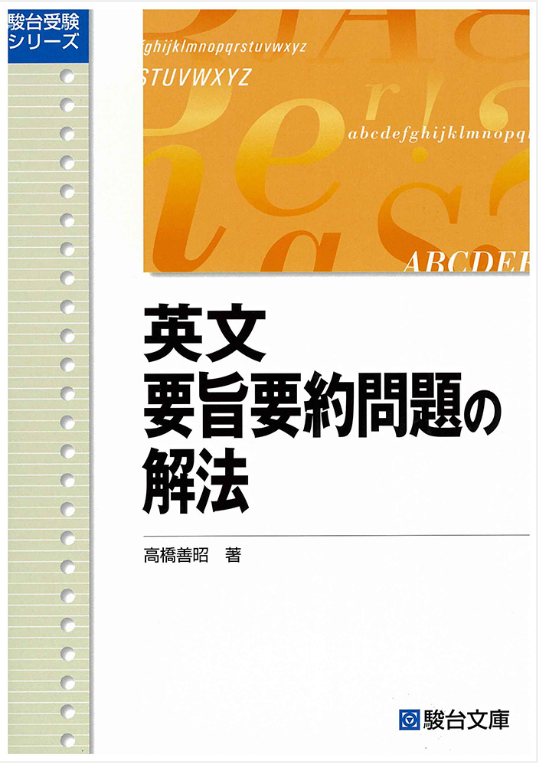
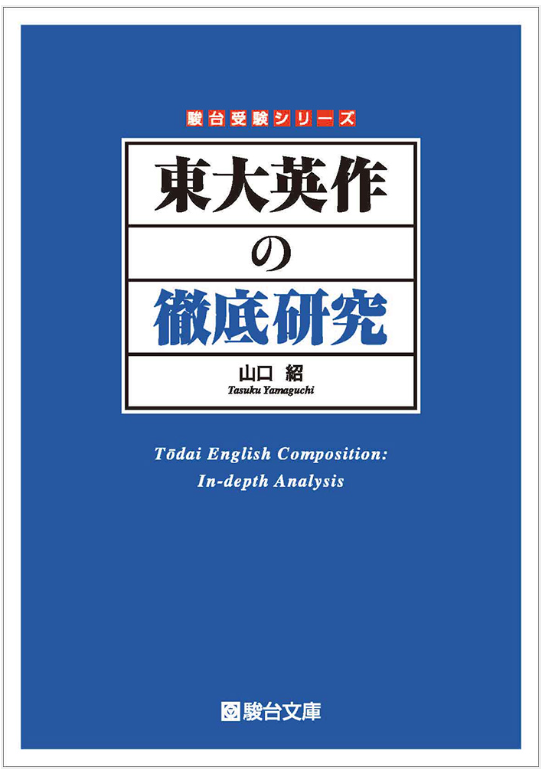
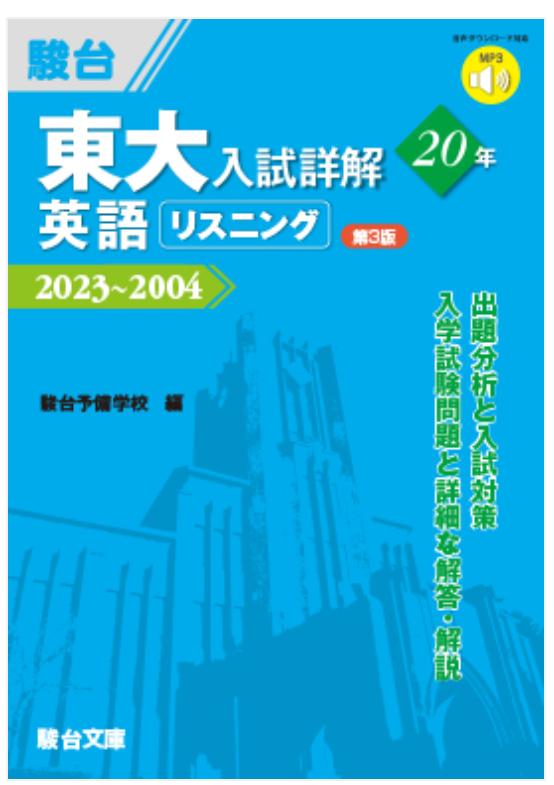
『英文 要旨要約問題の解法』 『東大英作の徹底研究』 『東大入試詳解20年 英語リスニング』
東京大学の英語は、文系・理系ともに440点満点中120点を占める、非常に重要な科目です。
120分という限られた時間の中で、要約・英作文・リスニング・長文読解といった多岐にわたる設問を処理しなければなりません。出題形式はオーソドックスですが、だからこそ基礎力・応用力・処理力のすべてが試されます。英語で安定して得点できるかどうかが、合否を左右すると言っても過言ではありません。
東大英語の中でも特に対策の成果が出やすい「要約」「英作文」「リスニング」3分野、それぞれのおすすめ問題集をご紹介します。
まず、要約対策におすすめなのが『英文 要旨要約問題の解法』です。PartⅠでは「どこに要点が書かれているか」「どのようにメモをとるか」など、答案作成の基礎となる読解力と思考力を丁寧に学べます。PartⅡには45問もの実戦問題が収録されており、演習を積みながら読解の型を定着させることができます。
英作文には『東大英作の徹底研究』が最適です。和文英訳・要約・情景描写など出題パターンごとに章立てされており、苦手分野を集中的に克服できます。加えて、コラムでは「前置詞のby」「基本動詞の使い分け」など、意外と見落としがちな知識を深めることができ、答案の完成度を高めてくれます。文法に不安のある人も、巻末付録で基礎をしっかり補えます。
リスニング対策には、『東大入試詳解20年 英語リスニング』を活用しましょう。東京大学の過去問だけを20年分収録した本書は、解説も丁寧で理解が深まります。音声はダウンロード可能なので、通学中や休憩時間に繰り返し聴き、耳を慣らしていく習慣を着けるとよいでしょう。
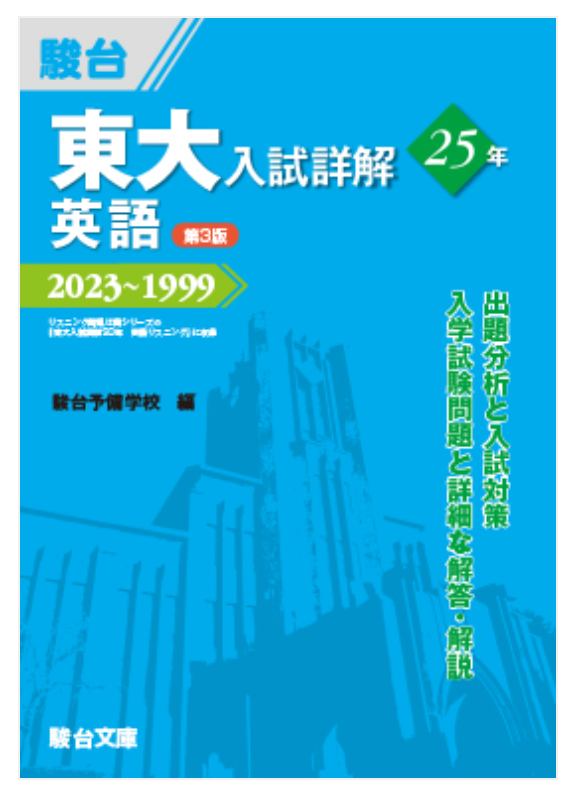
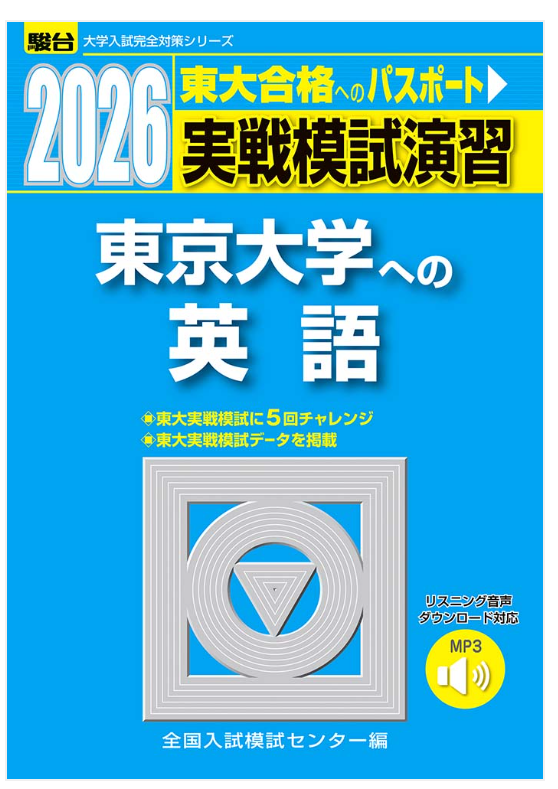
『東大入試詳解25年 英語〈第3版〉』 『2026・駿台 実戦模試演習 東京大学への英語』
最後に、リーディング全体の力を伸ばすには、『東大入試詳解25年 英語〈第3版〉』や『2026・駿台 実戦模試演習 東京大学への英語』といった実戦型の問題集にも取り組みましょう。演習後は、解説を熟読し、なぜその答えになるのかを深く理解することが大切です。ただ問題をこなすだけで満足せず、丁寧な振り返りを通じて、確かな得点力を身につけていきましょう。
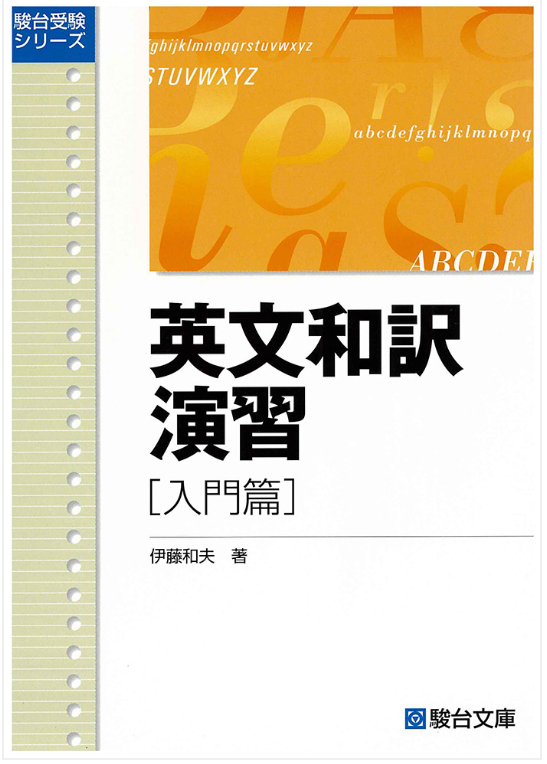
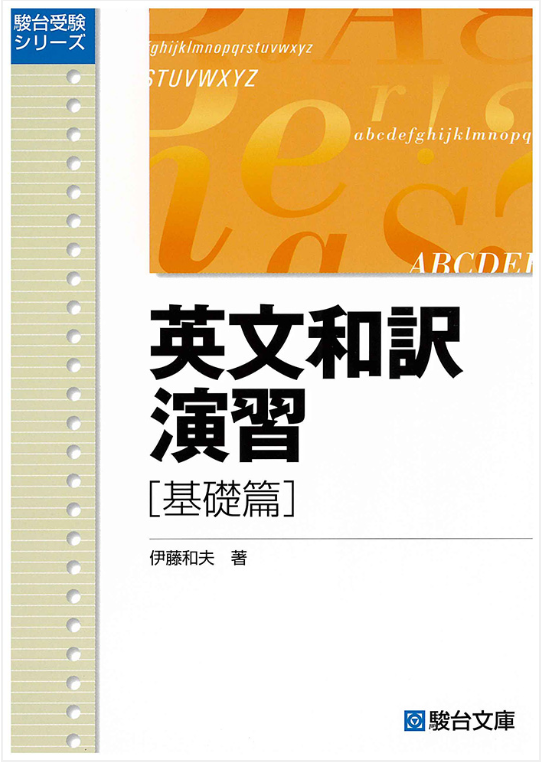
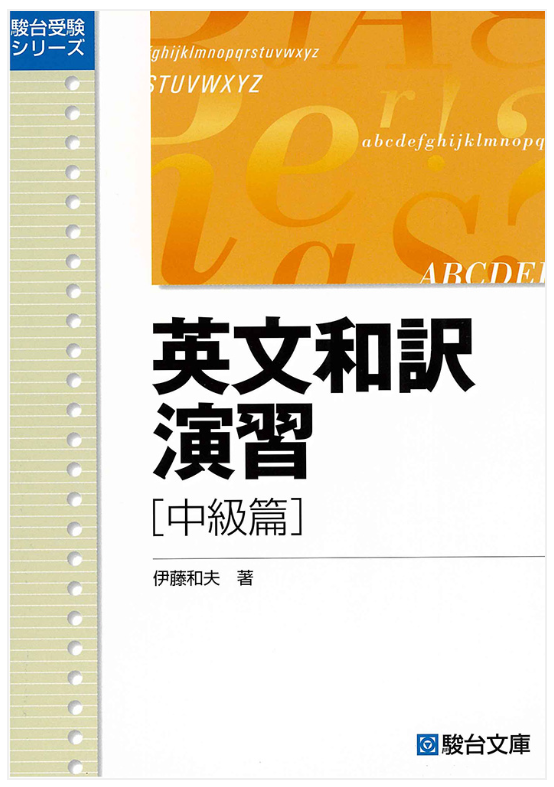
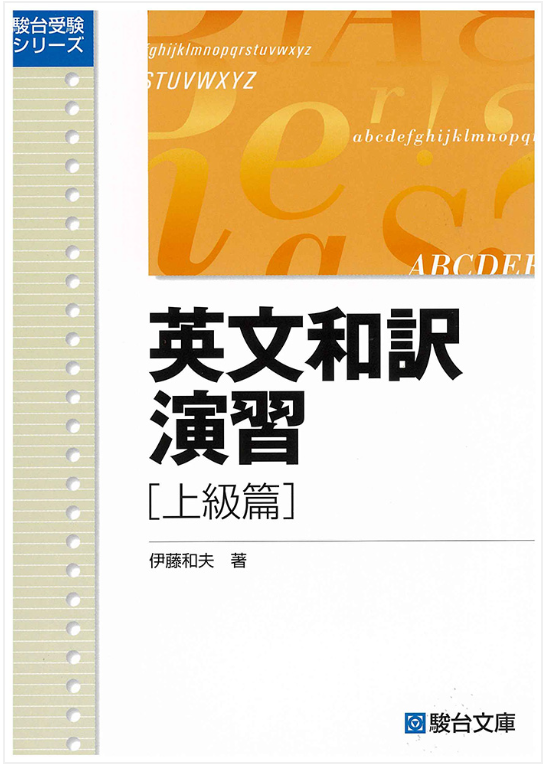
京都大学の英語は、設問数こそ少ないものの、ひとつひとつの問題に対して非常に高い精度と深い理解が求められるのが特徴です。特に和訳や英作文では、英文の細かな構造や論理を正確に捉える読解力と、それを適切な日本語・英語で表現する力が問われます。先に紹介した東京大学の英語が「速く・広く」英語を処理する能力を重視しているのに対し、京都大学では「深く・丁寧に」英語を読み解き、表現する力が重視されると言えるでしょう。
第1問、第2問で毎年出題される和訳問題への対策としておすすめなのが、『英文和訳演習』シリーズです。このシリーズは入門篇・基礎篇・中級篇・上級篇の4段階に分かれており、自分の現在の実力に応じて無理なく学習を進めることができます。初めて和訳に取り組む人は入門編から、構文の基礎がある程度身についている人は基礎編から始めるのがよいでしょう。京都大学の過去問に対応できる力は、中級編までを丁寧に仕上げることで十分に備えられますが、余裕がある人や英語を得点源にしたい人には、ぜひ上級編にもチャレンジしてほしいところです。
和訳の学習を進めるうえで大切なのは、「なんとなく読める」状態ではなく、「正確に構造を捉え、意味の通じる日本語に直せる」力を養うことです。そのためには、必ず自分の訳をノートに書き出し、模範解答や採点基準と照らし合わせながら、自分の弱点を客観的に把握していくことが効果的です。このシリーズには、詳しい解説や採点例も掲載されており、自学自習にも適しています。
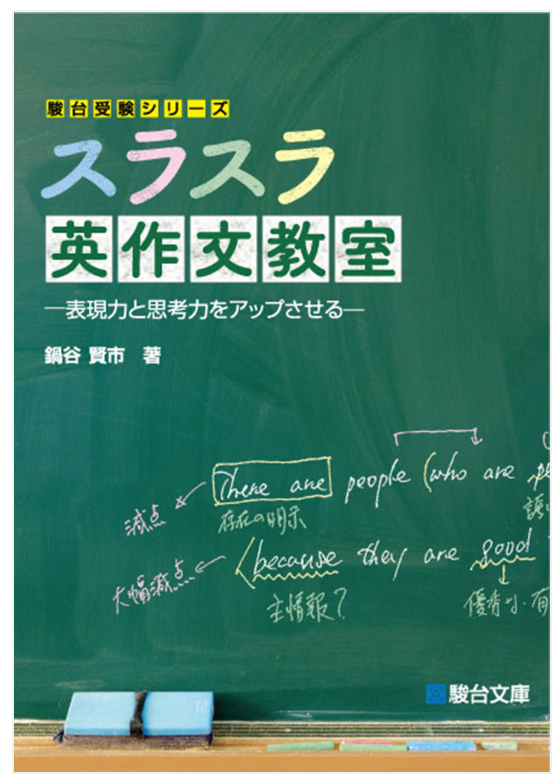
また、京都大学で毎年出題される英作文の対策には、「文系個別試験(二次試験)対策に ライティング参考書」で紹介した『スラスラ英作文教室』の活用がおすすめです。与えられた日本語文を瞬時に英語に変換する練習を繰り返すことで、限られた試験時間の中でも論理的かつ自然な英語で書く力が身に着きます。和訳と英作文、それぞれの答案作成力を丁寧に鍛えていくことが、京大英語攻略への確かな一歩となります。
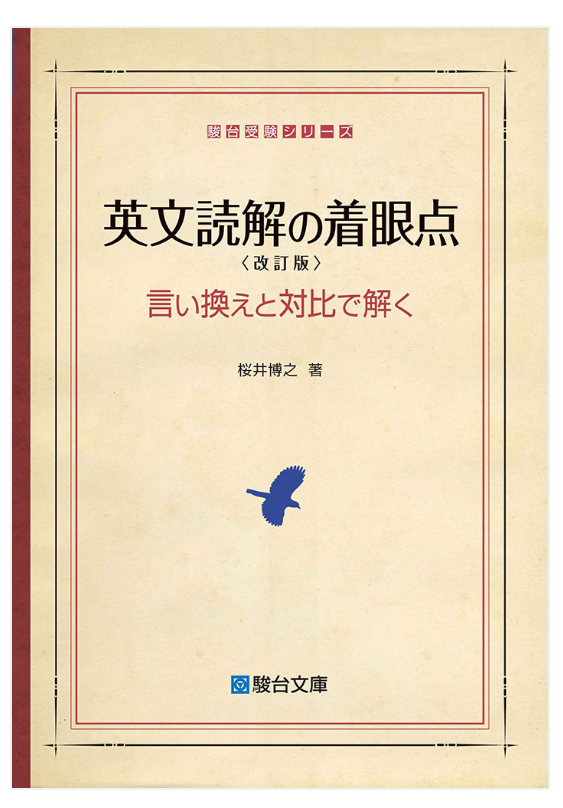
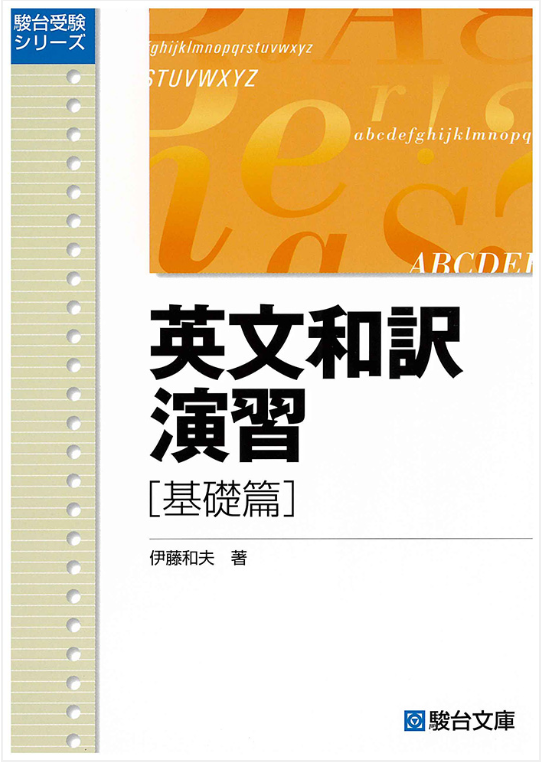
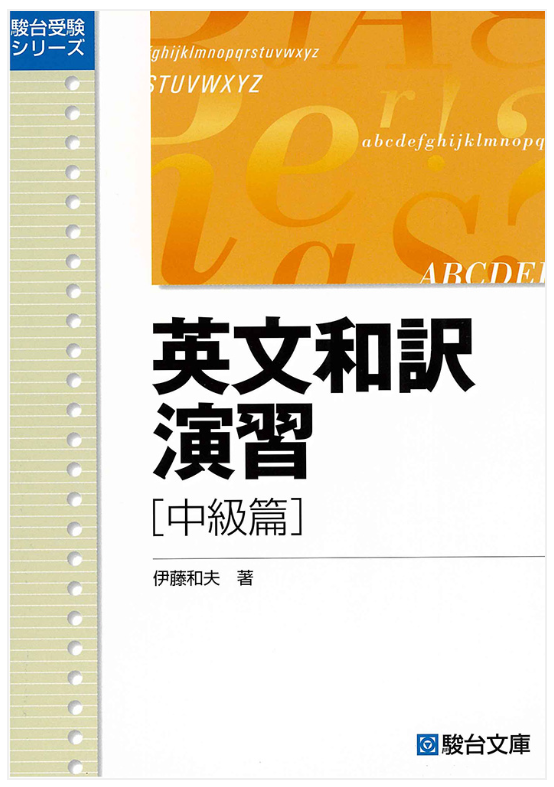
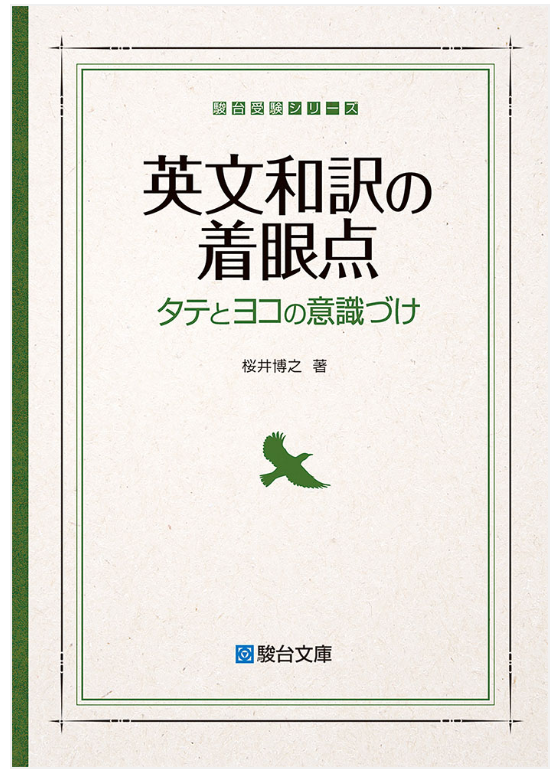
『英文読解の着眼点〈改訂版〉-言い換えと対比で解く-』『英文和訳演習』【基礎篇】 【中級篇】、『英文和訳の着眼点 ―タテとヨコの意識づけ―』
旧帝大と呼ばれる国立大学群(北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学など)では、記述力や論理的思考力を問う本格的な英語試験が課されます。問題形式は大学ごとに異なりますが、多くの大学で長文読解・和訳・英作文・文法の力が総合的に求められる点は共通しています。共通テストだけでなく、個別試験(二次試験)で確実に得点を積み上げられるかが、合否の分かれ目となります。
まず、長文読解力の養成には、『英文読解の着眼点〈改訂版〉-言い換えと対比で解く-』がおすすめです。本文の論理構造を把握するための視点が豊富に紹介されており、「なぜその選択肢が正解なのか」を、根拠を持って説明できる読解力を鍛えることができます。
和訳対策には、『英文和訳演習』【基礎篇】や【中級篇】に加え、『英文和訳の着眼点 ―タテとヨコの意識づけ―』の活用も効果的です。本書では、「タテ糸=文脈上のつながり、ヨコ糸=構文上のつながり」という観点から英文をとらえ、全体の意味を踏まえた自然で的確な訳文を作る力を養うことができます。ノートに訳文を書き、模範解答と比較しながら修正していく学習法が有効です。
英作文には、『スラスラ英作文教室』が適しています。日英の語順の違いや基本構文の使い方に注意を向けながら、じっくりと自然な英文を構築する力を養う練習を重ねることができます。出題形式に合わせた模範解答例も豊富で、得点につながる表現力を磨くことができます。
文法の抜けを補うためには、『英文法基礎10題ドリル』を通じて知識の整理をしておくと安心です。文法問題が直接出題されない大学であっても、正しい英語表現の理解は全分野における土台となります。
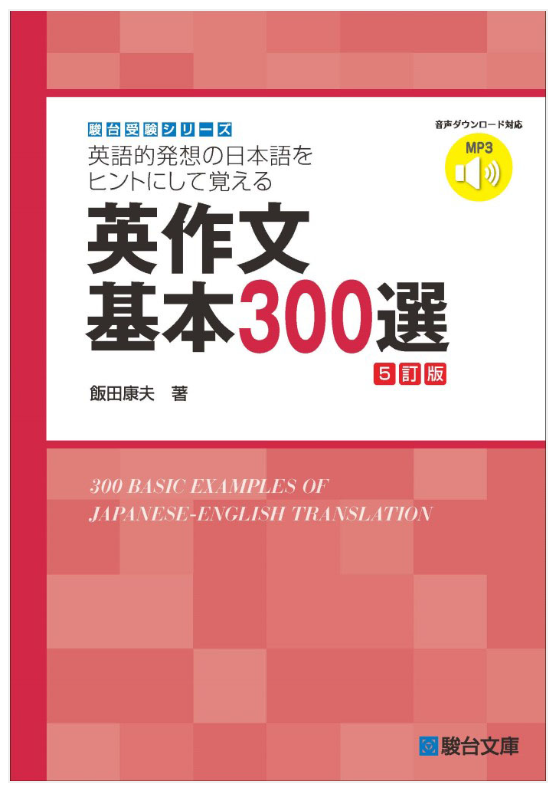
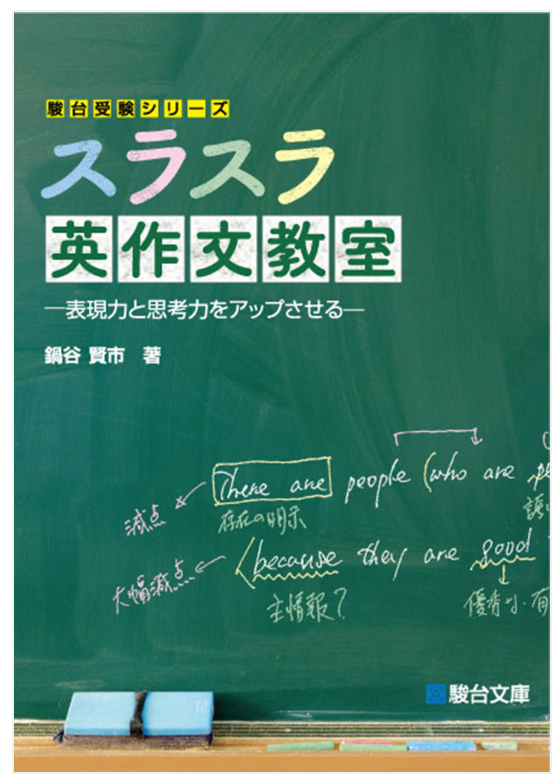
早稲田大学・慶應義塾大学の英語は、英文の分量・設問の難度ともに日本最難関クラスです。学部ごとに出題傾向は大きく異なりますが、共通して求められるのは、「正確な理解」と「速く読み解く力」の両立です。
近年は出題形式にも変化が見られます。たとえば、慶應義塾大学 理工学部では2023年に要約問題が出題され、和文英訳も同年以降、毎年出題されるようになりました。志望学部の傾向を早期に把握するためにも、高校3年生の春には過去問に目を通しておくことが重要です。最低でも3年分は確認し、形式や出題テーマの特徴を掴んでおきましょう。
ここからは、出題傾向に応じたおすすめの問題集・参考書をご紹介します。
まず、慶應義塾大学 理工・文学部や早稲田大学 法・政経で出題される英作文対策には、『英作文 基本300選〈5訂版〉』で基本表現を暗記し、『スラスラ英作文教室』で構成力と論理性を磨く学習がおすすめです。
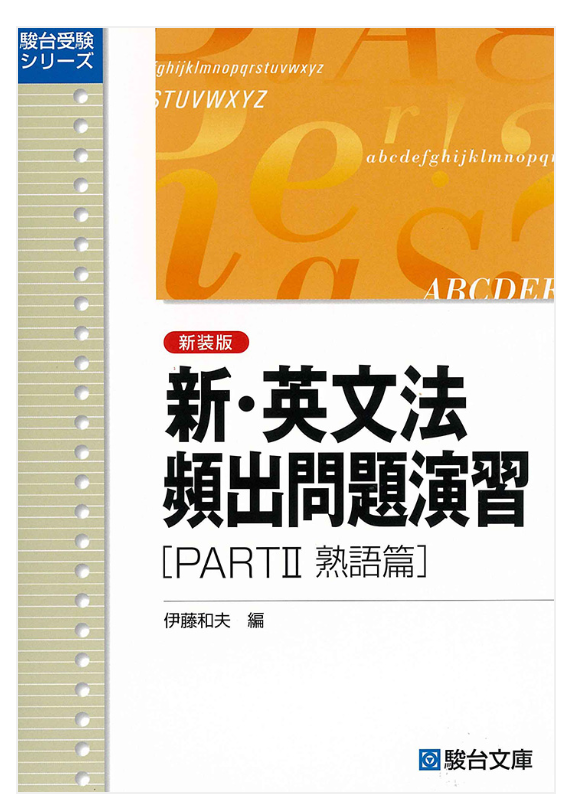
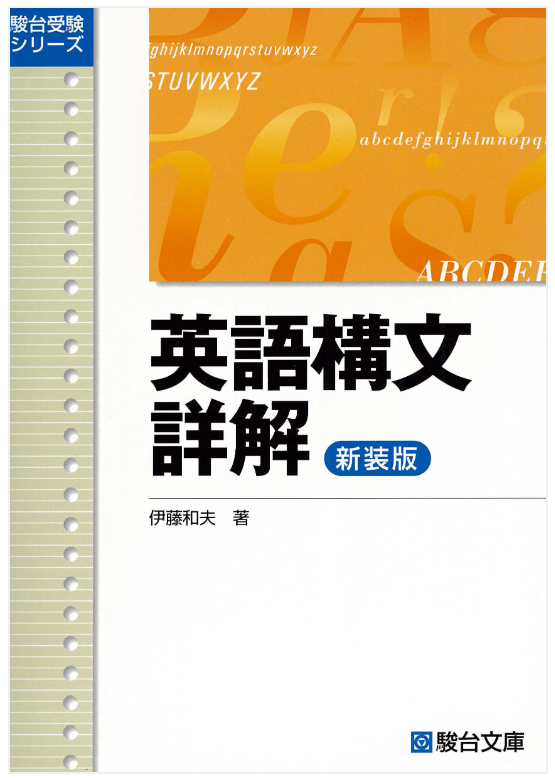
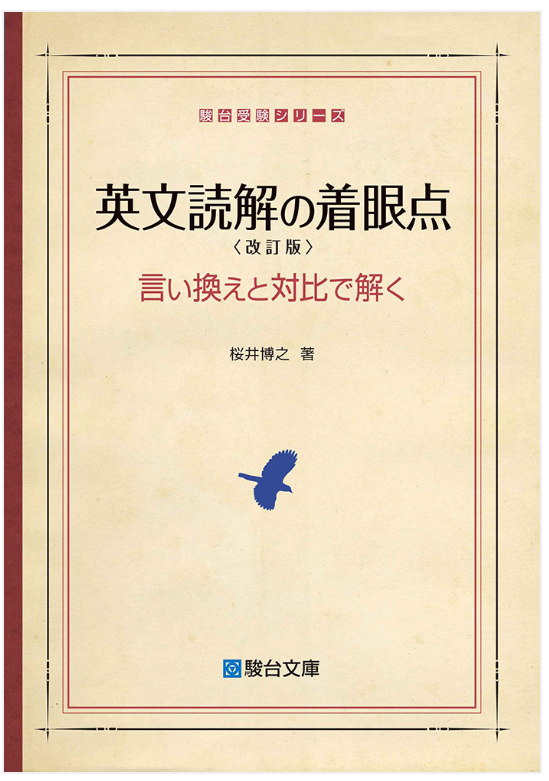
『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅡ 熟語篇』『英語構文詳解〈新装版〉』『英文読解の着眼点〈改訂版〉-言い換えと対比で解く-』
慶應義塾大学 商学部や早稲田大学 理工学部で出題される語彙・文法問題には、『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅡ 熟語篇』や『英語構文詳解〈新装版〉』で知識の定着を図りましょう。
読解対策には、『英文読解の着眼点〈改訂版〉-言い換えと対比で解く-』を活用して、論理構造の理解と情報のスピーディな整理力を身につけておくことが効果的です。
なお、早慶の入試では、問題集にはあまり登場しない語彙や構文が出題されることもあります。未知の表現に動じず、10月以降は過去問演習に積極的に取り組み、出題された知識をどん欲に吸収する姿勢が合格への大きな一歩となります。
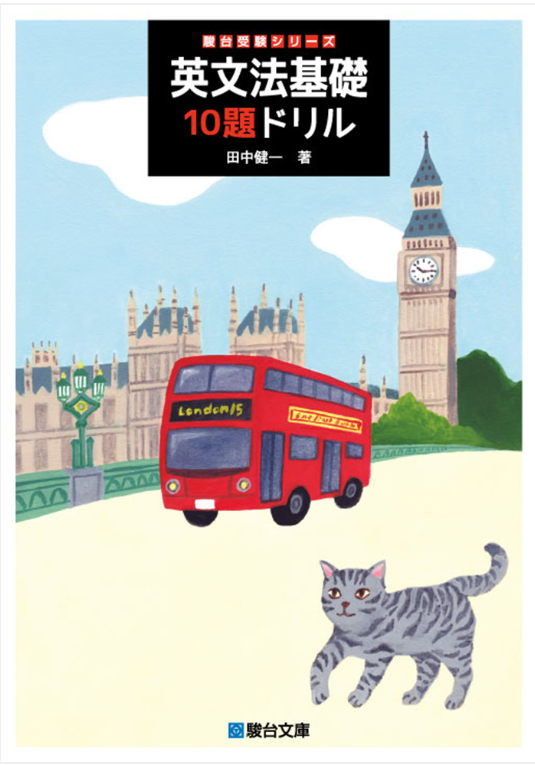
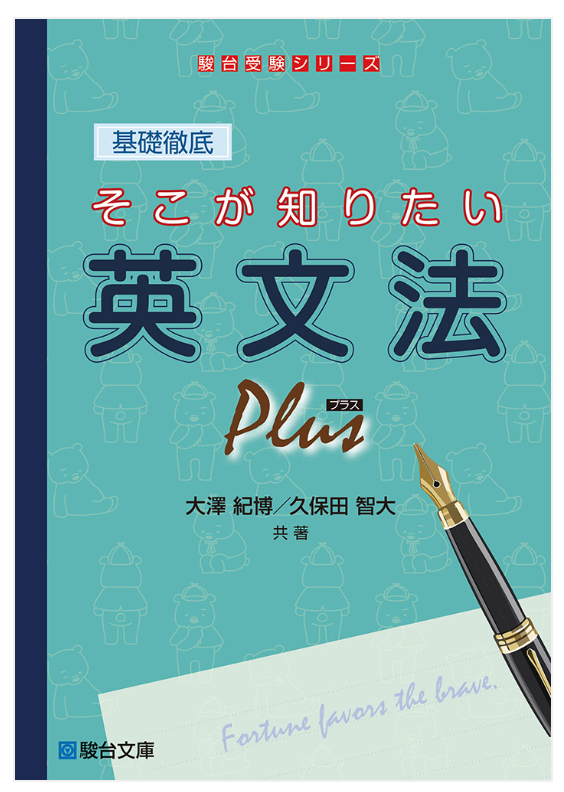
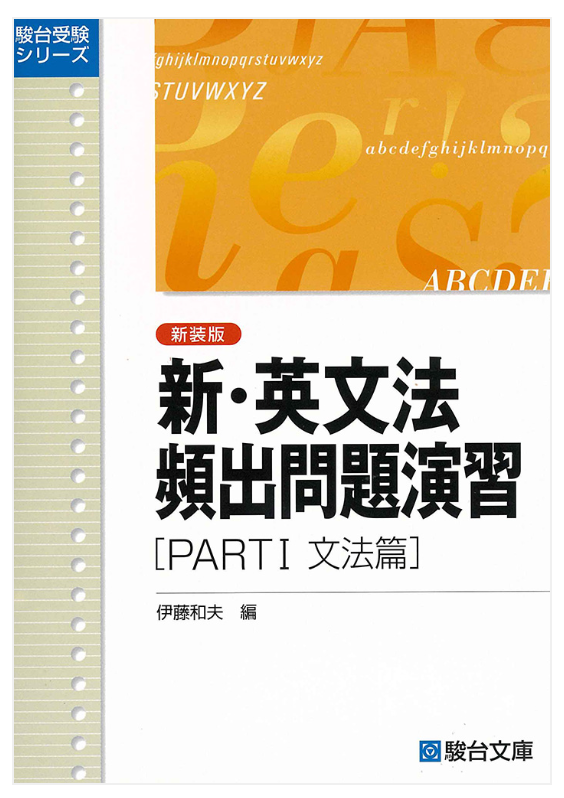
『英文法基礎10題ドリル』『基礎徹底 そこが知りたい英文法 プラス』『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅠ 文法篇』
GMARCHと総称される大学(学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政 ※立教は英語の独自試験なし)では、長文読解を中心に、文法・語法・語彙・会話文など、多様な問題形式が出題されます。一見すると標準的な出題に見えますが、実際には「読み取りの精度」や「基礎の徹底度」が求められ、決して油断できません。得点の差は、こうした基礎力の差や、小さなミスをどれだけ防げるかにかかっています。
まず、文法・語法の得点を安定させるには、『英文法基礎10題ドリル』で知識の抜けを確認し、『基礎徹底 そこが知りたい英文法プラス』で苦手分野を重点的に補強しましょう。さらに、『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅠ 文法篇』に取り組めば、実際の入試に近い形式で実戦力を養うことができます。
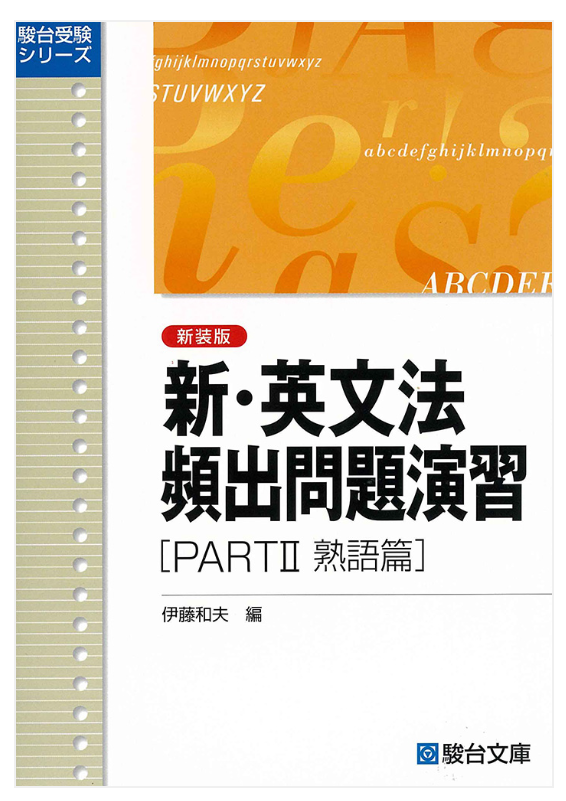
語彙や熟語も合否を分ける重要な要素です。『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅡ 熟語篇』を活用し、選択肢に惑わされない語感と知識を身につけていきましょう。語彙力が不足していると読解の正確性が落ち、設問での失点にも直結します。
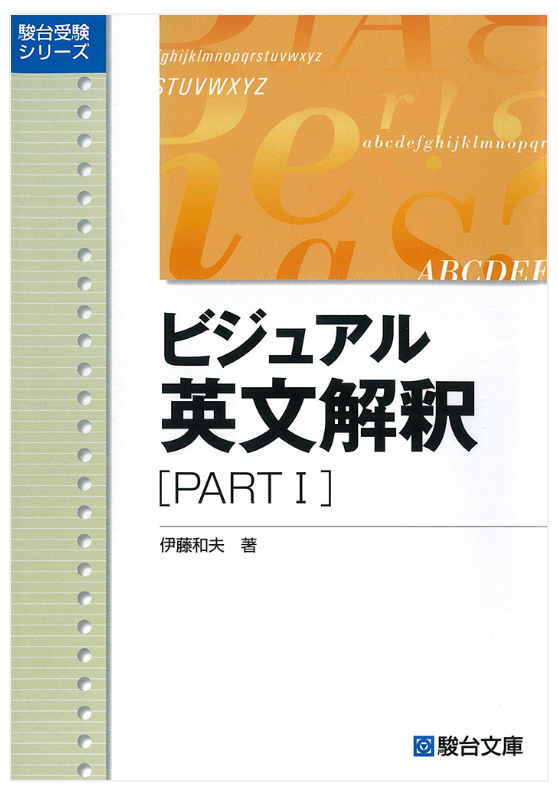
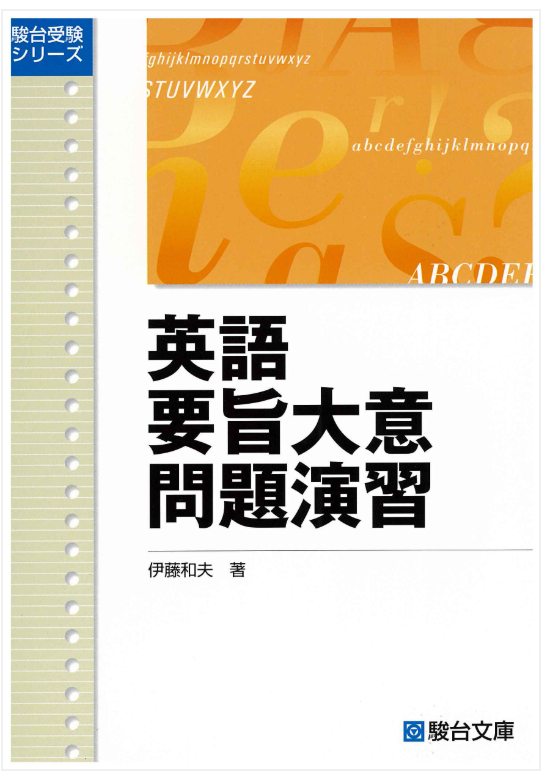
『ビジュアル英文解釈 PART I』『英語要旨大意問題演習』
読解力を高めるには、『ビジュアル英文解釈 PART I』の活用がおすすめです。構文の理解があいまいなまま読み進めてしまうクセを防ぎ、文の構造を意識して正確に読み解く力を養うことができます。また、過去問演習に入る前の段階で、段落ごとの要点を整理する力をつけておくために、『英語要旨大意問題演習』に取り組んでおくのも効果的です。高校3年生の夏休みなど長期休暇を利用して学習を進めておくと、秋以降の過去問演習が格段にスムーズになります。
GMARCH合格に求められるのは、「基本を正確に、丁寧に積み重ねる力」です。問題集や参考書を通じて、自分の弱点を客観的に把握し、毎日の演習を一つひとつ確実にこなしていきましょう。
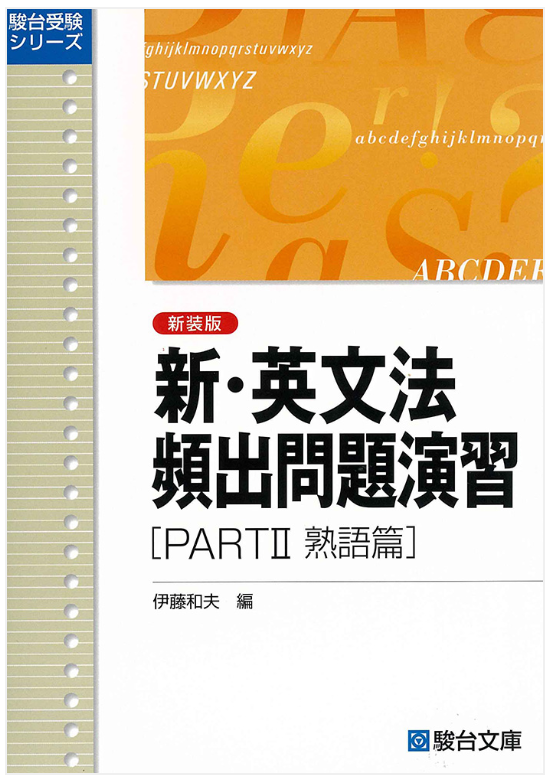
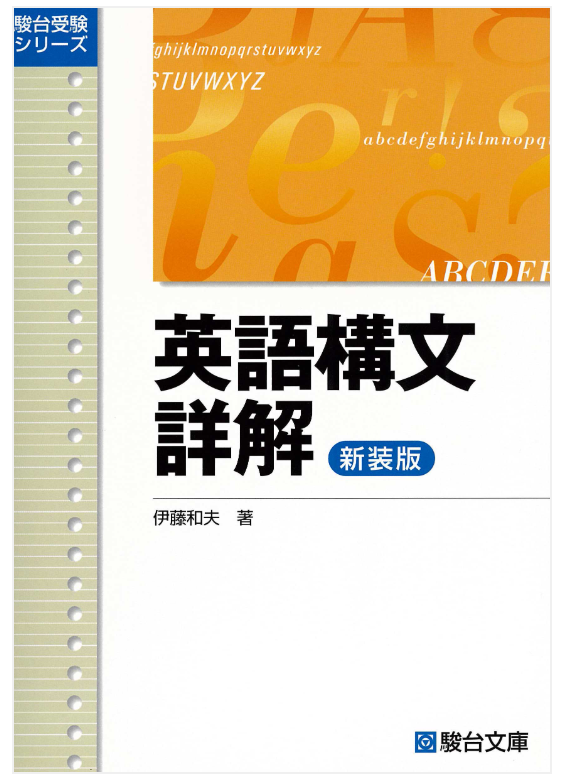
『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅡ 熟語篇』『英語構文詳解〈新装版〉』
理系科目に多くの時間を割く必要がある医療系学部志望者だからこそ、英語は「効率よく、確実に仕上げる」ことが合格への鍵です。特に私立医学部を中心に、英語は高難度かつ配点の高い科目であり、早めの基礎固めと戦略的な対策が欠かせません。
医療系学部の英語では長文読解が重視され、出題される英文には医療・倫理・健康・環境といった社会性の高いテーマが多く含まれます。背景知識に加え、文構造を正確に捉える力、そして語彙力が問われます。また、大学によっては発音・アクセント問題や自由英作文が出題されることもあり、形式の多様さにも対応する必要があります。
対策方針を早めに固めるために、高校3年生の春までには志望大学の過去問に一度目を通しておくと安心です。特に医学部を目指す場合は、高校2年生のうちに文法・語法・読解・英作文の基礎を完成させておくのが理想です。
使用する教材は目的別に選びましょう。
英作文対策には『英作文 基本300選〈5訂版〉』で表現の型を身につけ、『スラスラ英作文教室』で論理的な構成力を鍛えます。
語法や構文理解には『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅡ 熟語篇』や『英語構文詳解〈新装版〉』が効果的です。
発音・アクセント対策には『英語の発音・アクセント総仕上げ〈三訂版〉』を、和訳問題には『英文和訳演習』【中級篇】や【上級篇】を活用し、記述精度を高めていきましょう。
日東駒専レベルの英語入試では、空所補充や語句整序(並べ替え)といった文法力を問う設問の比率が高いのが大きな特徴です。日本大学の英語では、個別学部日程(A方式)でも全学部日程(N方式)でも、文法・語彙に関する基本的な問題が多く出題されます。こうした設問で問われる内容の多くは標準レベルであり、難問奇問はほとんど見られません。したがって、文法問題で確実に得点を積み重ねられるかどうかが、合否に直結する重要なポイントとなります。日本大学の文法問題で安定して8割程度の得点が取れるようになっていれば、基礎力はおおむね仕上がっていると考えてよいでしょう。
まずは『英文法基礎10題ドリル』に取り組み、解説を丁寧に読みながら問題演習を進めましょう。その中で、自分の知識に抜けやあいまいな部分がないかを確認し、不足している内容はしっかり補っていくことが大切です。特に苦手な分野が見つかった場合は、『基礎徹底 そこが知りたい英文法プラス』を活用し、知識を体系的に整理・定着させておくと安心です。
基礎を固めた後は、『新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PARTⅠ 文法篇』や『PARTⅡ 熟語篇』で実戦的な演習に取り組みましょう。語順整序に苦手意識がある方には、『英語構文詳解〈新装版〉』も併用することで、構文理解を深めながら得点力を高めることができます。
日々の学習で得た知識や間違えたポイントは、ノートに整理しておき、定期的に見直す習慣をつけましょう。特に土日や模試直前の復習時間を活用すると、効果的に記憶を定着させることができます。文法問題で安定した得点力を身に着けることが、合格への確かな一歩となります。焦らず丁寧に、基礎から積み重ねていきましょう。
AIの発達により、翻訳アプリや自動通訳の精度は大きく向上しています。「英語ができなくても何とかなる時代」と言われることもありますが、実際には、自分の力で英語を理解し、使いこなせることの価値は、むしろ高まっていると言えるでしょう。
英語ができれば、大学での学びはもちろん、将来の仕事や国際的な場面でも活躍の場が広がります。AIは便利なツールですが、相手の意図をくみ取ったり、自分の考えをきちんと伝えたりするには、自分自身の言語力が必要です。
こうした力は、すぐに身につくものではありません。日々の積み重ねが何より大切です。そのためにも、問題集や参考書を活用して、基礎からしっかりと力をつけていくことが欠かせません。ポイントが整理されていて、繰り返し学べる教材は、着実に力を伸ばすための大きな助けになります。
英語は一度身につければ、一生の財産になります。今取り組んでいる一冊を、自分の武器に変えていきましょう。コツコツ続けた努力は、きっと未来の自分を支えてくれるはずです。
\ 駿台公式SNSをフォロー /
編集担当が選ぶピックアップ記事
 八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所
八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。
プラスティー公式サイト