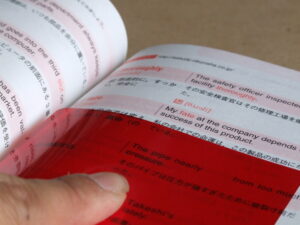「法学部」と聞いて、どんなイメージを持つでしょうか?「弁護士になるための場所」「法律をひたすら暗記する」といったイメージを抱いている受験生は少なくないかもしれません。
しかし、それは法学部の一側面にすぎません。法学部の学びは、単に法律の知識を増やすだけでなく、社会の複雑な問題を論理的に解決する力を養う、非常に実践的で奥深いものなのです。
この記事では、法学部で身につく特別な能力から、法律の具体的な学び、そして卒業後の多様なキャリアパスまで解説していきます。
法学部で身につく「法的思考力(リーガルマインド)」とは?

法学部の学びを語る上で欠かせないのが、「法的思考力」、通称「リーガルマインド」と呼ばれる力です。これは、単に法律の知識を覚えることではありません。
「法的思考力」とは、法律の知識をもとに、物事を客観的・多角的に捉え、論理に基づき最適な解決策を導き出す思考プロセスのことを指します。
この力は、法曹三者(弁護士・検察官・裁判官)はもちろんのこと、あらゆる職業で役立ち、現代社会を生き抜くための強力な武器となります。
では、どうすればこの「リーガルマインド」を身につけることができるのでしょうか?
法学部では、授業で判例(過去の裁判の事例)を読み解き、その判決がなぜ下されたのかを深く考察する「判例研究」や、特定のテーマについて学生同士が議論し合う「ゼミ」などを通じて、この力を徹底的に鍛えていきます。
たとえば、ある民事裁判の判例を取り上げてみましょう。
「AさんはBさんに土地を売却したが、実はその土地には重大な欠陥があった。この場合、AさんはBさんに対してどのような責任を負うべきか?」
このような事例について、学生はまず民法などの関連法規を調べ、過去の類似判例を参考にしながら、「Aさんの行為は民法の『瑕疵担保責任』に該当するのではないか?」「Bさんの損害賠償請求は認められるか?」といった点を論理的に検討します。
そして、自分の意見を明確な根拠とともに発表し、他者の意見を聞いて議論を深めていくのです。
このような学びを繰り返すことで、「法律の条文をただ暗記するのではなく、それを現実の問題にどう適用するか」という、生きた法律の知識を身につけていきます。
このスキルは、卒業後、企業の契約交渉や組織内の問題解決、そして私生活でのトラブル対処に至るまで、生涯にわたってあなたを支え続けるでしょう。
法的思考力は、あらゆる事柄に対して、「なぜだろう?」「本当にそうだろうか?」と疑問を持ち、論理的に答えを探究する姿勢を養う上で、非常に大切なものだと言えます。
法学部で学ぶ「法律」の全体像
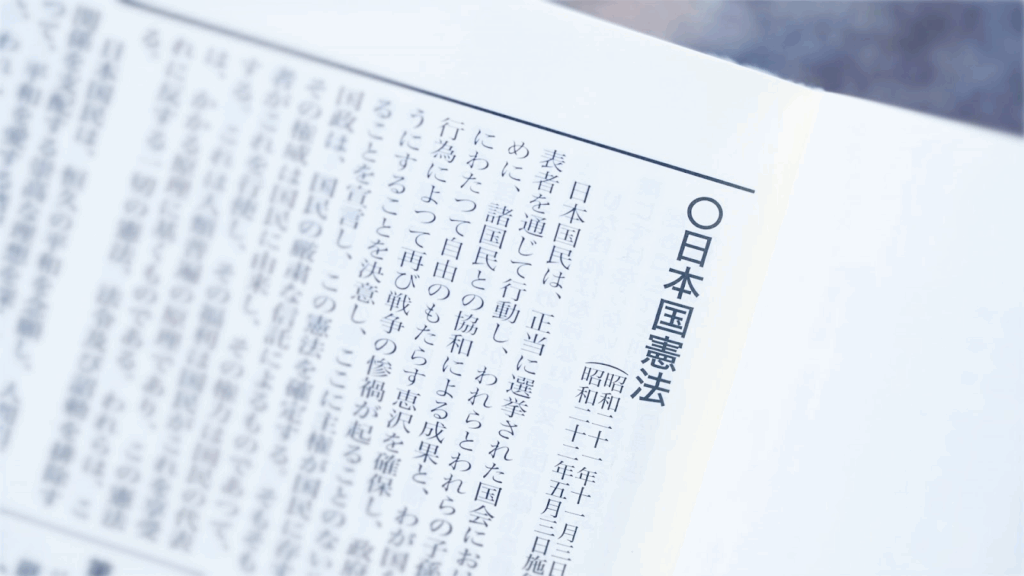
法学部の学びの土台となるのが、「基本六法」と呼ばれる以下の6つの法律です。これらは、さまざまな法律の基礎となり、私たちの社会生活を支える根幹をなしています。
これらの法律を学びながら、法学の歴史や本質を研究する「基礎法学」、国際的な問題に対応するための「国際法」など、多岐にわたる専門分野に触れていきます。
1. 憲法
日本の国家の仕組みや、国民の基本的な権利・義務について定めた最も重要な法律です。国と個人の関係を学び、国政のあり方や人権について深く考えます。
憲法は、他の法律がすべて従わなければならない「法の王様」のような存在です。たとえば、表現の自由や思想の自由など、私たちが当たり前のように享受している権利は、すべて憲法によって保障されているもの。
法学部では、これらの権利がなぜ重要なのか、そしてそれが侵害されたときにどうすればいいのかを、歴史的背景も踏まえて多角的に考察します。
2. 民法
個人と個人の関係を規律する法律です。財産の売買や貸し借り、結婚や相続など、私たちの身近な生活に関わるルールを学びます。
民法は、日常生活の「困った」を解決するための法律だと言えるでしょう。たとえば、「フリマアプリで商品を購入したら、説明と違うものが届いた」という場合、民法の売買契約に関する規定に基づいて、どのように解決すればいいのかを考えます。
3. 商法
企業活動に関わる法律です。会社を設立・運営するためのルールや、株主・経営者の関係などを学びます。
現代社会は多くの企業活動によって成り立っています。商法は、会社の設立から運営、資金調達、M&A(企業の合併・買収)といった、ビジネスにおける重要なルールを定めている法律です。商法の知識は、将来企業で働く上で、大きな強みとなるでしょう。
4. 民事訴訟法
民事(個人間のトラブル)の裁判手続きを定めた法律です。民法などで解決できない紛争を、どのように裁判所で解決するかを学びます。
トラブルが当事者間の話し合いで解決しない場合、最終的には裁判所に持ち込まれることがあります。民事訴訟法は、その際にどのような手続きで裁判が進められるのか、証拠はどうやって提出するのかといった、裁判のルールを定めています。
5. 刑法
犯罪と刑罰について定めた法律です。どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるのかを学びます。
刑法は、私たちの社会の安全を守る上で不可欠な法律です。たとえば、「人の財布を盗む」という行為がなぜ犯罪(窃盗罪)になるのか、その行為にどんな刑罰が科されるのかを学びます。
刑法を学ぶことで、社会の秩序維持のあり方について深く考えるきっかけとなるはずです。
6. 刑事訴訟法
刑事事件の捜査や裁判の手続きを定めた法律です。警察による逮捕や検察官の起訴、裁判の進め方などを学びます。
ニュースでよく耳にする「逮捕」「起訴」「裁判」といった一連の流れは、すべてこの法律に基づいて行われています。刑事訴訟法は、犯罪を裁くという国家の権力行使が、公正かつ適正に行われるためのルールを定めているのです。
多様な選択肢!法学部に設置されている主な学科

「法学部」とひとくくりに言っても、多くの大学では複数の学科が設置されており、それぞれに特色があります。
自分の興味や将来の目標に合わせて、最適な学科を選ぶことが重要です。ここでは、法学部に多い主な学科とその学びについてご紹介しましょう。
法学科:法律のスペシャリストを目指す王道
法学科は、法律そのものを体系的に深く学ぶ学科です。基本六法を徹底的に学び、法律の理論や解釈、過去の判例から学ぶ問題解決の手法を身につけます。
法律の専門家である弁護士や検察官、裁判官を目指す人はもちろん、法律知識を活かして企業の法務担当者や公務員を目指す人にも最適な学科です。法律という学問の面白さや奥深さを存分に味わいたい人に強くおすすめします。
政治学科:政治の仕組みから社会を動かす力を学ぶ
大学によっては、法学部に政治学科が設置されている場合があります。政治学科では、選挙制度や国際政治、行政の仕組みなど、政治に関する幅広い知識を学びます。
法律が社会のルールだとすれば、政治はそのルールをどのように作り、動かしていくのかを考える学問だと言えるでしょう。
法律と政治は密接に関わっており、政治の動きが法律に影響を与えることも多々あります。この学科では、政治と法律の両方の視点から社会を分析する力を養うことができるのが大きな特徴です。
外交官や国会議員の秘書、ジャーナリストなど、社会を動かす仕事に興味がある人にとって魅力的な選択肢です。
国際関係法学科:グローバルな課題を法的に解決する
国際関係法学科は、グローバル化が進む現代において、国際的な問題に法的な視点からアプローチする学科です。
国際法、国際取引法、国際人権法などを中心に学び、国家間の紛争解決、貿易、環境問題など、地球規模の課題を解決するための知識とスキルを身につけます。
将来、国連職員や国際協力の仕事に就きたい人、外資系企業で活躍したい人、海外で活躍する弁護士を目指したい人など、世界を舞台に活躍したいと考えている人に最適です。英語や第二外国語の習得にも力を入れている大学が多く、実践的な語学力も同時に磨くことができます。
その他の学科:大学ごとの特色ある学び
上記以外にも、大学によっては「公共政策学科」など、特色ある学科を設置している場合があります。これらの学科では、法律や政治、経済、社会学などを横断的に学び、現代社会が抱える複雑な問題(環境問題、少子高齢化、貧困など)の解決策を多角的に探究します。
特定のテーマに特化した学びができるため、大学のパンフレットやウェブサイトで、どのような学科やコースが用意されているかを事前に調べてみることが重要です。
法学部のキャンパスライフと学び方
法学部の学びは、高校の授業とは大きく異なります。高校のように先生がすべてを教えてくれる受け身の姿勢ではなく、自分で積極的に学びを深めていく姿勢が求められるのが、法学部の学び方です。
法学部の中心的な学びの場は、講義とゼミ(演習)です。
講義では、数百人規模の大きな教室で教授の話を聞き、法律の基礎知識を身につけます。このとき、教授は法律の条文やその背景にある考え方、主要な判例などを解説していきます。講義の予習・復習が、法律知識を定着させる上で非常に大切になります。
一方、ゼミは少人数の学生で特定のテーマについて深く議論する場です。自分の意見を発表したり、他者の意見を聞いて思考を深めたりします。このゼミが、前述の「リーガルマインド」を養う上で非常に重要な役割を果たします。
たとえば、「少年法は厳罰化すべきか?」というテーマで議論するとします。
学生は、少年法の目的、過去の改正経緯、犯罪統計、海外の事例など、多角的な情報を集めます。そして、「厳罰化すべき」と考えるグループ、「現行のままで良い」と考えるグループに分かれ、お互いの意見をぶつけ合います。
このような議論を通じて、私たちは、「ひとつの正解はない」ということを学びます。なぜなら、法的な問題には、常に異なる利害関係や価値観が存在するからです。多様な視点から物事を捉え、最適な解決策を模索する力が、このゼミを通じて磨かれていくのです。
また、法学部では多くの専門用語を学ぶため、レポートや論文の作成を通じて、正確な言葉で論理を組み立てるトレーニングを積みます。
試験では、暗記した知識を問われるだけでなく、与えられた事例に対して法的根拠に基づいた解決策を提示する「事例問題」が出題されることも多く、日頃からの予習・復習が不可欠です。
法学部で目指せる将来のキャリアパス

法学部で身につく法的思考力や論理的思考力は、あらゆる分野で求められる汎用性の高いスキルです。そのため、法学部を卒業した後の進路は非常に多様だと言えるでしょう。
法律の専門家を目指す道もあれば、一般企業や公務員として社会に貢献する道もあります。ここでは、代表的なキャリアパスをご紹介します。
法律の専門家「法曹三者」への道
弁護士、検察官、裁判官の3つを総称して「法曹三者」と呼びます。法曹になるためには、司法試験に合格する必要があります。司法試験の受験資格を得るためには、法科大学院(ロースクール)に進学するのが一般的です。
法科大学院は、法律の専門家を養成するための大学院で、学部で学んだ法律知識をより実践的に深めることができます。
大学によっては、「法曹コース」を設けているところもあります。これは、大学を3年で早期卒業し、法科大学院に直結する専門コースです。法曹を目指す強い意志がある人にとっては、このコースも選択肢の一つとなります。
公務員として社会に貢献する
公務員は、社会のルールを守り、より良い社会を築くために働く存在です。法学部で培った法律知識は、国家公務員、地方公務員、警察官など、多くの公務員の仕事で直接的に活かすことができます。
特に、行政の仕組みや憲法・行政法などを学ぶことは、公務員試験の対策としても非常に有利です。また、論理的に物事を考え、文章で表現する能力は、公務員の職務において必須のスキルだと言えるでしょう。
一般企業で活躍する
法学部出身者は、一般企業でも高く評価されます。法律知識を活かし、企業の契約書の作成や交渉、コンプライアンス(法令遵守)体制の構築などを行う「法務部」で活躍する道があります。
また、金融業界や不動産業界など、法律と密接に関わる業界では、専門知識を持つ人材が特に重宝されます。
たとえば、企業の法務部では、他社との契約内容を検討したり、新しい事業を始める際の法的リスクを調査したりします。法学部で培った「法的思考力」は、これらの業務を遂行する上で不可欠な力です。
資格を活かして働く
法学部での学びは、さまざまな資格取得に役立ちます。行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁理士、税理士など、法律に関する多くの資格試験では、法学部で学ぶ知識がそのまま試験範囲となります。
これらの資格を取得することで、専門家として独立開業したり、企業内で専門性を発揮したりすることができます。資格取得は、あなたのキャリアの選択肢を大きく広げることにつながるはずです。
法律を専門としない道も
法学部の学びは、法律専門職や公務員を目指す人だけのものではありません。マスコミ、教育、ジャーナリズムなど、幅広い分野で法学部の出身者は活躍しています。
これは、法学部で培われる「物事を深く、多角的に分析する力」「論理的に思考し、自分の意見を明確に表現する力」が、どんな仕事においても役立つ汎用的なスキルだからです。
たとえば、ジャーナリストであれば、事件や社会問題を報じる際に、法的根拠に基づいて事実関係を整理し、読者に分かりやすく伝えることができます。また、教員であれば、社会のルールや仕組みを、より深く、説得力を持って生徒に教えることができるでしょう。
このように、法学部の学びは、あなたの可能性を限定するものではなく、むしろ「将来の選択肢」を大きく広げてくれるものなのです。
まとめ:法学部は「将来の選択肢」を広げる学びの場

法学部は、単に法律を暗記する場所ではありません。目の前の問題を客観的に捉え、論理的に解決する「法的思考力」を養う、非常に実践的な学部です。
この力は、弁護士や公務員といった専門職だけでなく、一般企業で働く上でも強力な武器となります。法学部の学びは、あなた自身の価値を高め、多様なキャリアパスを拓くための土台を築いてくれることでしょう。
ぜひ、各大学のウェブサイトやパンフレットもチェックして、あなたの興味に合う学びの場を探してみてください。未来の自分が、どんな社会で、どんな役割を果たしたいのかを考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
【参考コラム】
文理選択で後悔しないための完全ガイド~5つの決め方と先輩の失敗談から学ぶ将来設計
経済学部で何を学ぶ?将来性・就職先から気になる疑問まで徹底解説!