
執筆:八尾直輝
「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝
「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長
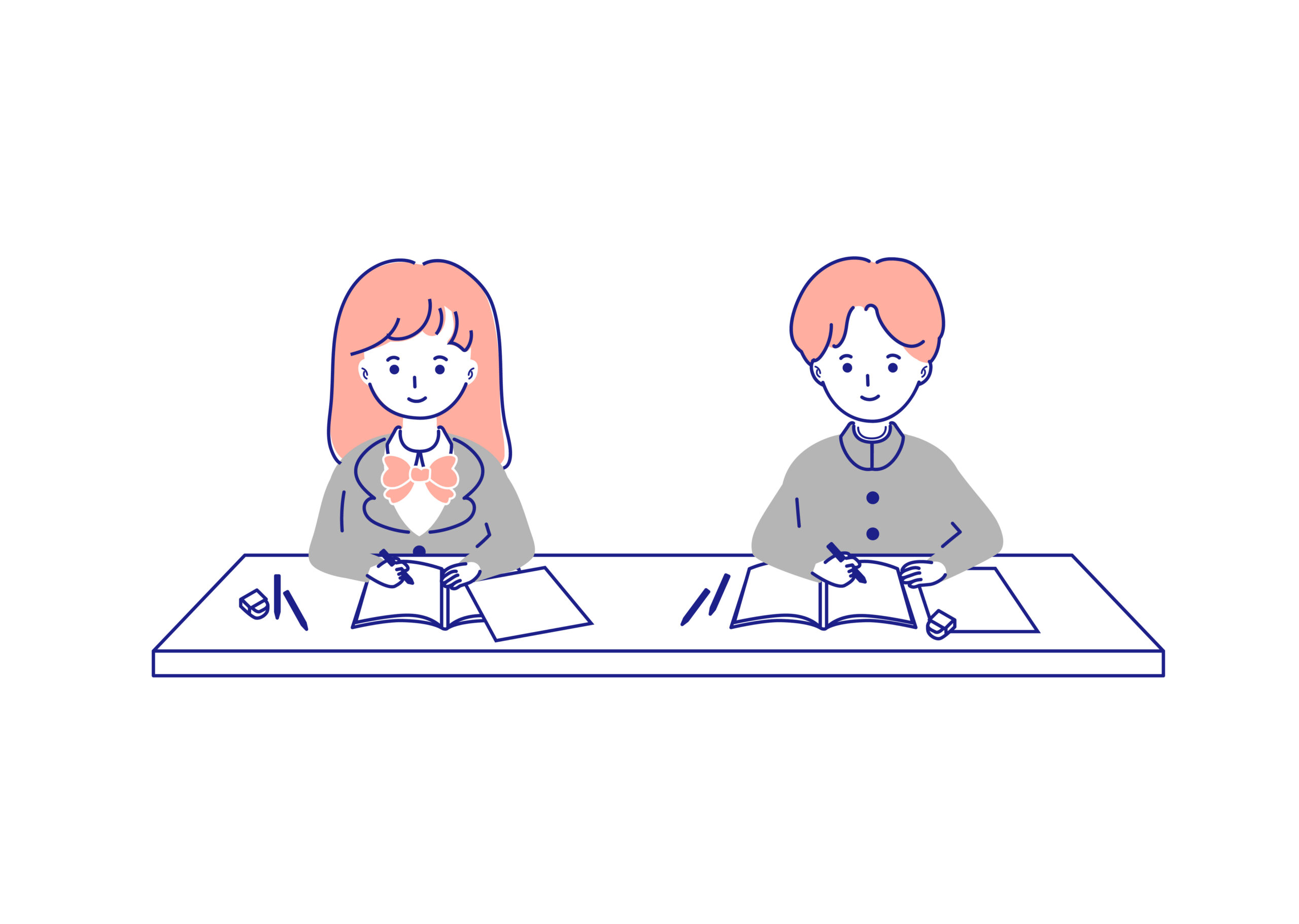
以前のコラムでは学習サイクルについて解説しました。学習サイクルとは「予習→授業→復習→テスト」の一連のサイクルのことで、これがうまく機能することが、「学習が順調であること」と定義しました。
「うまく機能する」とは、「できない」ことが「できる」ようになることであり、予習とは「『できない』と『できる』を分ける」ことだと解説しました。
予習は授業の準備です。「できないこと」をあらかじめ顕在化しておくことで、授業をより効果的にすることができます。
また、予習では「初見力」を磨くことができるのも見逃せない点です。思考力を伸ばす上で予習はとても重要な位置を占めているのです。
とはいえ、予習が求められない授業も少なくないと思います。
まず授業で講義を聞き、それをもとに復習するというスタイルも効果的な学習スタイルの1つです。学習時間に制約があるときは、復習を優先した方がいいことも少なくありません。
しかし、少しの予習をすることが授業を効果的にすることもあります。
事前テキストを読むだけで授業の大まかな流れが頭に入ったり、集中して聞くべきポイントが明確になることもあります。そういう意味で、予習は必須ではない授業でも自ら学習効率を向上させるために取り組むものです。
特に不得手な科目への苦手意識を克服するために、その科目を予習するのはとても効果的なやり方です。
学習サイクル(予習→授業→復習→テスト)で考えると、授業は「できない」を「できる」にすることと言えます。
また多くの場合、授業は長時間です。授業の受け方を改善することは、そのまま成績向上に直結します。そういう意味で授業は学習サイクルのなかでもっとも重要なフェーズなのです。
また、授業は復習の準備と考えることもできます。復習時にまとめノートを作成する生徒も少なくありませんが、授業中にまとめノートを作ってしまえば、帰宅後すぐに復習を始めることができます。
復習しやすい授業の受け方を追求することが、学習全体の効率を大きく押し上げると言っても過言ではありません。
ところでみなさんは「授業」と聞いてどのような形態を思い浮かべるでしょうか。
先生から直接講義を受ける対面授業を想像した人がもっとも多いかもしれません。また動画コンテンツ・オンライン授業などを想像した人もいるかもしれませんね。授業の形式には優劣はありません。個人の置かれた状況や、得意・不得意を考慮し適切な授業形式を選択するようにしましょう。
大切なことは「できない」を「できる」にすることであり、授業の形式は問題ではないからです。
そう考えると、自分で参考書を読むことも立派な「授業」と言えます。このような形式を「文献授業」と呼びます。
このやり方のメリットは、何よりも効率がよいことです。時間・場所を選びませんし、自分のペースで学習を進めることができます。質問できない・行間の理解を自分で埋める必要があるなどのデメリットもありますので、得意科目に向いているやり方と言えます。得意な科目は積極的に文献授業を取り入れてみてもいいかもしれません。
前回の記事で述べたように、授業には様々な型があります。
ここでは「文献授業・映像授業・対面授業」の3つの形式と、それぞれのメリット・デメリットをまとめます。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 文献授業 | 場所・時間を選ばず、自分のペースで学習できる。 | テキストの行間を自分で理解する必要があり、難易度が高い。 |
| 映像授業 | 自分のペースで学習できる。講師の解説を聞くことができ、わかりやすい。 | 講師に質問ができない。自分に合った教材を見つけるのが難しいときがある。 |
| 対面授業 | 講師から直接学べる。生徒の理解度に合わせて、柔軟に授業内容を変更することができる。 | 時間・場所の拘束がある。文献・映像授業と比較し、学習のスピードが劣るときがある。 |
得意科目は文献授業・映像授業で学習を進めることができる場合もありますが、苦手科目は個別の対面授業が有効なこともあります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合うようにカスタマイズすることが重要です。
ここまでの内容を踏まえ、以下に授業の受け方の見直し方をまとめます。
ぜひ自分の学習の見直しに活用してみてください。
1.授業の型を見直す
「文献・映像・対面」の3つの授業の型で、より自分の学習を効率化できないか考えてみましょう。
例えば映像授業では緊張感が足りないと感じる人は、集団の対面授業に変更したほうがいいかもしれません。
2.授業の受け方を見直す
同じ授業でも受け方によって成果は大きく異なります。授業が「復習の準備」となるように、授業中にやるべきことを整理してみましょう。
帰宅してすぐに復習を始めることができていないとしたら、それは授業中に復習の準備が不足しているからかもしれません。
3.予習のやり方を見直す
予習が求められていない授業でも、自ら予習をすることを検討してみましょう。
特に苦手科目は先に授業全体の概観を理解することで、授業中の詳細な解説を理解しやすくなることもあります。
\ 駿台公式SNSをフォロー /
編集担当が選ぶピックアップ記事
 八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所
八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。
プラスティー公式サイト