進路はあなたの学びたいこと、将来の夢を軸に選びたいものです。しかし、やりたいことが見つからない、まだ漠然としているという人も多いでしょう。
この記事では、学問選びや目標探しのヒントとなるトピックスを紹介します。
失敗・脱線があるから研究は面白い?【理学】【工学】
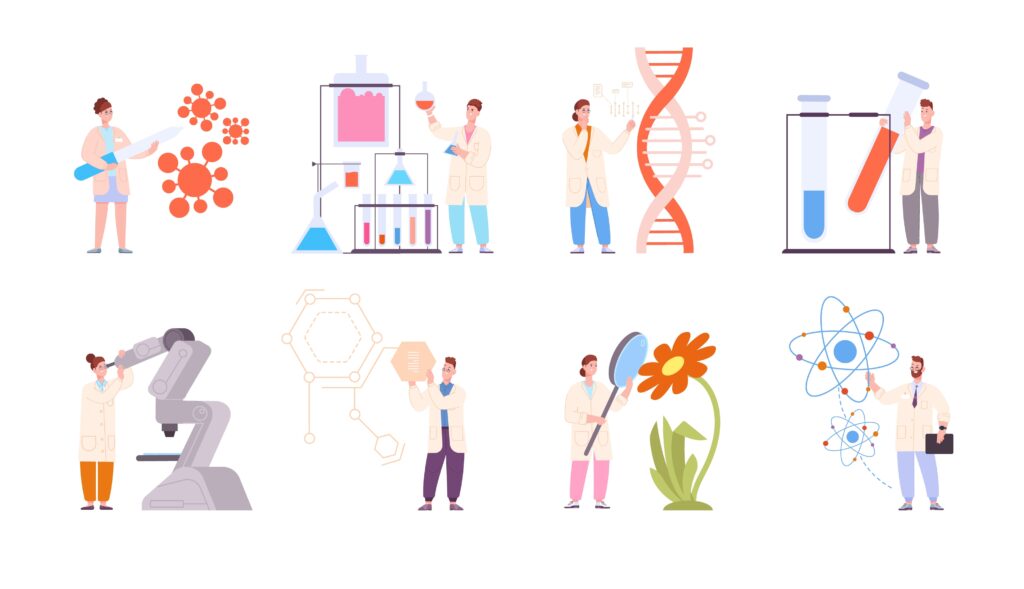
理学・工学の目的・魅力
理学は自然界の現象や物質の原理・法則の解明をめざす学問です。たとえば、素粒子のひとつニュートリノを研究することによって、宇宙のさまざまな謎が解明できるとされています。
一方で、理学(科学)の知見をもとに、世の中に役立つ技術やモノを創造するのが工学です。理学は基礎研究、工学は応用研究とよく区別されますが、明確に分かれているものではなく、研究の面白さは同じです。学生は実用的で目的がわかりやすい研究を好みがちですが、今はなにに役立つかわからないけれど、誰も解いたことのないテーマや問題に挑戦する基礎研究の面白さは、大学ならではの学びと言えるでしょう。
研究の大リーガーは続くか?
理学や工学の分野を中心に、日本人研究者がノーベル賞を受賞してきました。日本の基礎研究は世界から評価されてきましたし、モノづくりは日本の強みです。
しかし、近年では研究と技術の両面で、諸外国から遅れをとっているのではないかと懸念されています。産業界からは大学に対して、実用化にすぐに結びつく応用研究より、企業ではなかなか難しい基礎研究に期待する声も聞かれます。研究の地道な積み重ねなくして、山積する問題の解決や豊かな社会の実現はできません。
日本の科学・技術の国際競争力を高めると同時に、諸外国と手を携えて研究を進めていく必要があるでしょう。研究者にはグローバルな視点がいっそう求められており、活躍の場が広がっているのです。
一夜にして教科書が書き換えられる?
物質に質量を与える起源とされるヒッグス粒子の発見は、世界の素粒子物理学者たちが待ち望んだものでした。その発見は最後の素粒子、神の粒子とも呼ばれ、新聞各紙の一面を飾ったほどです。
ヒッグス粒子の存在を予言したピーター・ヒッグス博士とフランソワ・アングレール博士はノーベル物理学賞を受賞しましたが、ヒッグス粒子の発見が新たな謎を生み、物理学者たちは挑戦を続けています。そこには多くの日本人研究者、研究機関、企業も参加しており、物質の根源や宇宙の成り立ちの解明に皆さんが挑むチャンスが開かれています。
ドラマだけじゃない! 技術のスピンオフ
スピンオフドラマとは、本編から派生して生まれた続編のこと。技術開発でも、その過程で思いがけなく副産物が生まれたり、別の用途に転用されたりすることがあります。
たとえば宇宙技術では、固体ロケット点火用火工品技術が自動車のエアバックに、宇宙観測カメラ駆動技術が手術顕微鏡・内視鏡に活用されています。実は、数多く行われている実験の中で実際に実用化につながるのはほんのひと握り、一方で予想外の発見があったり研究テーマが脱線したり、好奇心を発揮した自由な研究が世界を変えていくことでしょう。
理学・工学で学べる学問分野
理学は、数学、物理学、化学、生物学、地学などから成り立ち、ミクロの世界から宇宙まで幅広いテーマに展開します。各々の分野が密接に関連しながら、自然界の真理の探究をめざします。
工学は、機械、電気・電子、情報・通信、材料、応用化学・工業化学、土木・建築、資源・原子力・エネルギーなどの分野が代表的ですが、医療やバイオテクノロジー、経営や金融など、社会生活のあらゆる場面を支えています。
人間は技術よりも頼りになる?【情報学】

情報学の目的・魅力
情報学は、(情報システムやアプリ、Webコンテンツなどを)「つくる」「使う」の両面からアプローチすることができます。
情報技術の進歩が著しい一方で、コンピュータウイルスによる攻撃やSNSによるトラブルなど、使う側からも考えるべき課題が多くあります。広くとらえれば、情報学は理系と文系の両方にまたがる学問と言えるでしょう。
人口知能(AI)にどこまでゆだねるべきかなど、倫理的な考察もいっそう重要になっています。
情報通信技術が時代を創る
5Gに続く6G(第6世代移動通信システム)の開発が進んでいます。2000年代に入り、通信の高速化や大容量通信が可能となったことで、スマートフォンが普及し、私たちのライフスタイルが大きく変わりました。
一方で、デジタルデトックス(一定期間、スマートフォンやパソコンなどから距離を置く試み)も提唱されています。このように情報学はさまざまな問題と接点をもちながら生活に影響を与えています。
人による最強のセキュリティ対策
マルウェア(ウイルスなど悪意のあるソフトウェアの総称)の感染や、不正アクセス、情報漏洩などの脅威を防ぎ、コンピュータやインターネットを安全に使うために行うのがセキュリティ対策です。サイバー攻撃による被害は巨額の経済的損失を生むだけでなく、公共的なサービスが停止すれば社会生活が大きなダメージを受けます。
たとえば、次世代の暗号技術とされる量子暗号など、セキュリティ対策の研究は進んでいますが、利用者側のリスクに対する意識と行動によって被害を減らすことができるのも事実です。IDやパスワードなどを信用させて人から直接聞き出したり、金融機関やクレジット会社などになりすましてメールを送り偽のホームページに誘導して個人情報を入力させたりする行為は、ソーシャルエンジニアリングと呼ばれ、その事例や対策の研究が期待されるテーマです。
AIは人間を超えるか
AIが人類を越える「シンギュラリティ」に、2045年には到達するだろうという指摘があります。対話型AIや生成AIが出現し、AIが人間にとってかわる社会が現実味を帯びてきたようにも思えます。
AIの利用や規制についての議論が、国際社会でも始まっています。多くの大学もAIについてメッセージを発信していますが、頼り過ぎず、AIを有効に活用しながら、学び続けること、新しいことに挑んでいくことが人間に課せられた使命と言えるでしょう。シンギュラリティの行方は、人間自身に委ねられているのではないでしょうか。
情報学で学べる学問分野
情報工学では、ハードウェアやソフトウェアの開発・設計、そのほかコンピュータの基本・応用技術(ネットワーク・通信、インターネット、画像処理、セキュリティ対策など)を学びます。データサイエンスとは、膨大なデータを分析し、社会課題の解決やビジネスに役立てる研究や実践です。情報リテラシーやデータを扱う能力は、どのような職業に就いても必要になるでしょう。
人類の歴史は環境問題の歴史?【環境学】

環境学の目的・魅力
環境学は、人と環境との関係や影響を探求し、持続可能な社会の実現をめざす学問です。地球や自然環境に限らず、社会環境、都市環境など、人や自然の営みを広く対象とした複合的・学際的な学びと言えます。
たとえば環境経済学では、地球温暖化や環境汚染などによって生じる経済的損失や、環境保全と経済発展を両立する政策などのテーマに取り組みます。興味・関心に応じて幅広いテーマに挑戦でき、社会貢献を実感できることが環境学の魅力でしょう。
古代文明の盛衰と環境問題
持続可能な開発目標(SDGs)が盛んに取り上げられているように、環境は現代的な問題のようにとらえられがちですが、人が自然を利用しながら文明を築いてきた歴史を見ても、人類の普遍のテーマと言えるでしょう。
前2000年頃に成立したクレタ文明(ミノス文明)は、メソポタミアに対する重要な木材供給基地となったことも繁栄の要因とされています。メソポタミアは文明の発展とともに森林資源が減少していました。そして、クノッソス(クレタ文明の中心地)でも木材が不足するようになり、文明が衰退し、当時まだ森林を有していたとされるミケーネへと文明の中心が移っていたという説があります(参考:ジョン・パーリン「森と文明」)。
環境保全か、経済成長か
環境破壊がこのまま進めば、私たちも古代文明と同じ運命をたどるのでしょうか?
地球環境問題は、世界がひとつになって取り組む必要があります。これまでは、地球温暖化の問題のように、温室効果ガスの排出量が歴史的に多い先進国と、経済的に弱く、温暖化リスクも大きい発展途上国との間で対立がみられました。しかし、近年では地球環境問題に対する危機意識が高まり、第21回国連気候変動枠組条約締約国会議においてパリ協定が採択され、「すべての国(国連加盟国)による取り組み」として合意が実現しています。企業に対しても、地球環境問題への意識を社会や市場が厳しく評価するようになりました。持続可能な社会の実現に向けて、環境への取り組みと経済活動との両立が求められています。
GX(グリーントランスフォーメーション)への期待
GX(グリーントランスフォーメーション)とは、経済産業省が提唱する脱炭素社会に向けた取り組みです。日本は2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現をめざす(=温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする)ことを宣言しています。そのための活動を経済成長のチャンスとするために、経済社会システム全体を変革していこうという取り組みがGXであり、温室効果ガスの削減やカーボンニュートラルについてのノウハウ(ルールや仕組み)や技術などの産業競争力を高めていくことをめざしています。
環境学で学べる学問分野
自然環境を対象にしたテーマは、地球温暖化、異常気象、海洋・大気などの汚染、水問題、生態系や森林の保全などが挙げられます。また工学的な分野では、建築やデザインと融合したアプローチもあります。人文・社会科学の観点からは、環境問題に関する法や政策、経済や企業活動、教育や福祉などの問題に取り組むことができます。学べるテーマが多岐にわたるため、目標を明確にしたうえで志望校を検討しましょう。
まとめ
「なぜ?」と疑問をもったり、生物や天体に触れて「きれい!」と感動したり、好奇心や感性を存分に発揮して学べるのが、自然を対象とする学問の魅力です。社会貢献の機会も多い分野ですから、専門以外のことにも幅広く目を向けて研究のヒントを見つけましょう。















