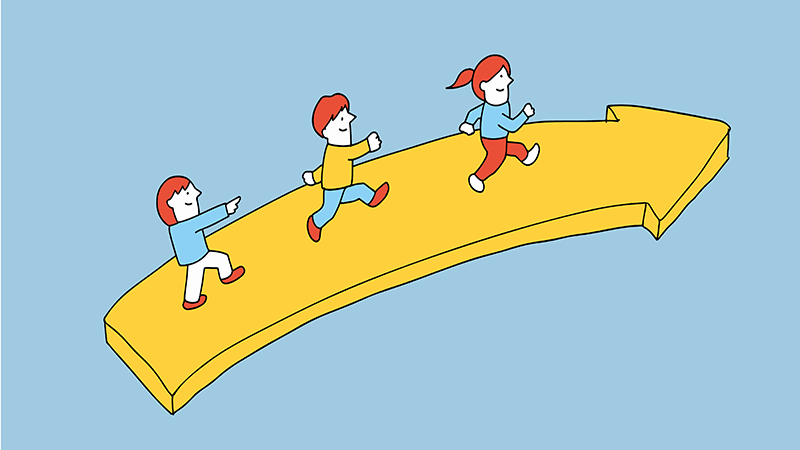進路選択で大事なことは、他者のアドバイスやさまざまな情報を効果的に活用することと、
自分をしっかりと見つめ直し、自己管理しながら勉強に取り組むことです。
そのためにも、長期的な展望を踏まえて自分を活かす目標を定めることが重要です。
高校生はこれから実力が伸びますから、自分を信じて、夢に向かって進んでいきましょう。
志望校の選び方
志望校はいつ、どのように決める?
現在高1・2生の人は、大まかには高3になるときには決めておくとよいでしょう。受験という長い道のりの中で、目標を決めて取り組むことが大切です。できれば今の点数や偏差値にとらわれず、その後の実力の伸びを考慮して、高めの目標を設定することがポイント。それによって学習意欲も高まります。高3からは、入学者選抜要項なども参考にしながら絞り込んでいきます。
志望校は「学びたいこと」を優先に、それを実現できる大学・学部を選ぶことが基本。入学後の目標を明確にした上で志望校を検討していきましょう。第一志望を決めたら安易な変更は禁物です。仮に志望校の難易度レベルを下げたとしても、ほかの受験生も同様の動きをするため、結果的に同じような競争になります。やはり、第一志望を軸にした学習を続けてほしいと思います。
文系・理系、選択科目を決める際の注意点は?
選択科目、あるいは文系・理系を、苦手科目を基準に選ぶ人もいるのではないかと思います。高3生は現実的な選択も必要になりますが、高1・2生は進路選択の幅を狭めないよう前向きに考えたいものです。必要な科目を履修していないために志望大学等を受験できないこともあります。さらに大学の学習では教科・科目を横断したテーマにも取り組むことになります。
国立大か私立大か?
国立大は、研究環境の充実や学生の基礎学力の高さなどの魅力があります。一方、私立大は独自の伝統やカラーを持っています。やはり、オープンキャンパス等に参加して、自分に合うか実際に確かめることが有効でしょう。いずれも意欲ある学生や社会で活躍する卒業生との交流も刺激になります。さらに幅広い学部学科を設置する総合大学であれば、多角的な学びが可能です。
私立大の選抜方法をどう選ぶ?
私立大では、受験生に配慮した多様な選抜方法が用意されています。共通テスト利用方式型で合格すれば、一般選抜まで目標大学に絞った勉強が可能になるでしょう。とは言え、チャンスが増えて必ずしも安心ということではありません。全学部統一入試では、多くの学部に合格する人がある一方、結果を出せないで苦戦することも。やはり確かな実力を身につけることが第一です。
関連記事
共通テスト利用入試とは?メリットと知っておきたい受験の知識
インターネットの情報の活用法は?
インターネットをはじめとしてさまざまな入試情報が発信されています。気を付けたいのは、これらの情報に左右されて、志望校の選択や勉強方法などで自分を見失ってしまうことです。インターネットの情報はすべてが必ずしも自分に当てはまるとは限りません。高校の先生方や駿台の進路アドバイザーに相談するなど生きた情報も大切にしましょう。
やりたいことを見つけるためには?
やりたいこと、学びたいことは自分の興味・関心が軸になるのは当然ですが、「世の中のために自分が役に立てること」など、社会とのつながりの中で考えることもできます。そもそも、目標を考える機会を作っていないのか、情報が少なくて決められないのかなど、自分の状況を客観的に見直すことも大切です。目標は今後変わってもよいので、柔軟に考えてみましょう。
目標はモチベーションのエネルギーになります。明確な目標や高い意識を持った受験生を大学が歓迎するのは当然です。「やりたいことが見つからない」と悩む人もいる一方で、逆に自分の興味だけにこだわり過ぎて選択の幅を狭めている人も見られます。本を読んだり、人の意見を聞いたり、まずは視野を広げて考えてみましょう。
学習の進め方
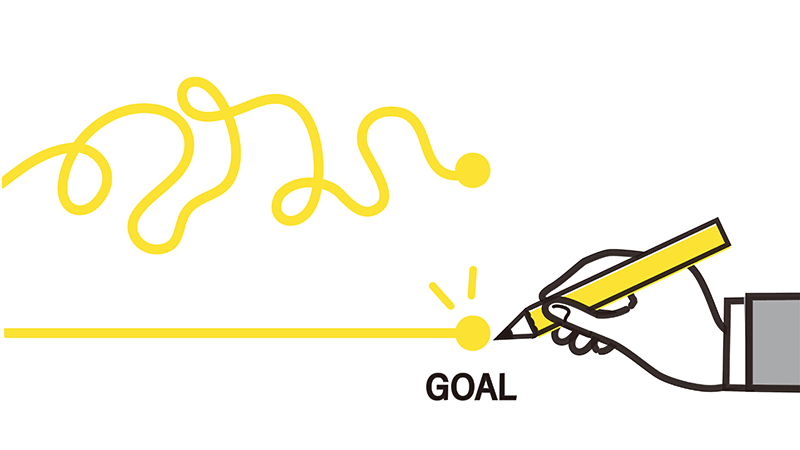
勉強計画を立てる上でのアドバイスは?
高3になると、「夏休みには苦手科目の克服」「秋から過去問の演習」といった計画を立てる人が多いでしょう。ただ本番入試のゴールを意識し過ぎるあまり、計画をプレッシャーに感じてしまうこともあります。今日、今週とやるべきことをしっかり決め、進行を振り返りながら取り組むことがポイント。予備日を設けておくと気持ちに余裕が出てきます。
関連リンク
【大学受験スケジュール表付】スケジュール管理と勉強の進め方
受験勉強で最も大切なことは?
あれこれ参考書や問題集に手を付けたが中途半端で投げ出してしまったという失敗談をよく聞きます。「授業に集中した」「予習・復習を確実にこなした」と多くの合格者は話しています。つまり基礎を疎かにせず、あたり前のことを確実に行っていくことが最も効果的な方法ということです。難関大と言えども日ごろの授業が大切なことは言うまでもありません。
特に高1・2生で気をつけることは?
高3では志望校の問題傾向と対策を踏まえた学習が必要になりますが、これも高1・2で基礎学力をしっかりと確立しておくことが前提になります。国・数・英の主要教科の学習を徹底するとともに、苦手科目を作らない、早めに苦手を克服することを心がけましょう。特に高1生は、学習の習慣や自分なりの勉強スタイルを身に付けることが大切です。
部活をどうする?
部活動と両立しながら難関大合格を果たした先輩も多くいます。共通するのは、部活動をしながらも学校の授業を疎かにしないこと、朝の始業前や休み時間など、時間を有効に使って学習していることなど、できない理由をつくらないことです。受験生の自主性や意欲が問われる中で、部活動やボランティア活動など、学習以外のさまざまな経験を積んでいくことは有効です。
模試をどう活用する?
模試は自分の実力や大学の合格可能性を知る上で役立つことはもちろんですが、それだけではありません。模試直後、答案返却時、しばらく経ってからと最低3回は復習することで、実力が定着します。高卒生と一緒に受験する模試では思うような成績が出ないこともありますが、大切なのはその後の実力の伸びにつなげること。評価だけに一喜一憂する必要はありません。
関連リンク
模試とは?実力把握、予行演習、目的に合わせた選び方と使い方
記述力を高めるには?
大学入試では、記述力がクローズアップされています。学問ばかりでなく社会に出てからも必要となる能力です。記述の練習を重ねることに加えて、先生の添削を積極的に受け、内容を改善していくように努めましょう。また総合問題などで科目や分野を融合した出題も見られるようになり、社会の出来事などに問題意識をもって触れることも大切になっています。
AI教材の特徴は?
AIやICTを活用した教材は今後ますます普及していくでしょう。これらは基礎の理解や苦手科目の克服など、傾向や原因を分析した上で、個人に最適なメニューを提供するような学習に適しています。通学時間やすき間時間などを有効に使えることも特徴です。さらに講師の授業を受けることで相乗効果が期待できます。駿台が提供するツールをぜひ活用してください。
スランプを乗り越えるには?
入試は本番では一人だけの戦いですが、受験勉強のプロセスではある意味で団体戦と言えます。仲間と刺激し合ったり支えあったりして勉強することでスランプも乗り切ることができるでしょう。夢や悩みを大いに語り合ってください。一緒に合格するという気持ちが好結果を生みます。また家族のサポートなどに対して感謝の気持ちも忘れないようにしたいものです。